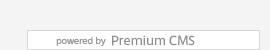HOME» ブランド対談 #09 »知財とマーケティングから見るブランドマネジメント
ブランド対談 #09
知財とマーケティングから見るブランドマネジメント

知財とマーケティングから見るブランドマネジメント
足立氏は、日本コカ・コーラ株式会社で法務に従事され、また国内外の知財・法務におけるブランドマネジメントにも関わっておられます。また田中氏は、元電通のマーケティングディレクターという異色の経歴を経て、現在は大学院でブランド・マネジメントの啓蒙と研究に携われています。知財とマーケティング、それぞれの専門とお立場からの視点で、ブランドとは何か、そして日本の企業のブランド戦略について語っていただきました。
注) 文中の足立氏の発言内容はすべて足立氏個人の見解であり、所属される組織や団体の見解でありません。
 田中氏: ブランドマネジメントは1つのものではなくて、いろんなアプローチがあると思うんですね。ひとつは経営トップから見て、全社的にそのブランドをどう位置づけるか、或いは企業ブランドをどうマネジメントするかといった企業が管理するところのブランドマネジメント。
田中氏: ブランドマネジメントは1つのものではなくて、いろんなアプローチがあると思うんですね。ひとつは経営トップから見て、全社的にそのブランドをどう位置づけるか、或いは企業ブランドをどうマネジメントするかといった企業が管理するところのブランドマネジメント。
もう一つはマーケティングを行うことによって、ブランド価値を高めましょうというマーケティング視点でのブランド戦略。さらにもう一つは知財の面からのブランドマネジメント。これは以前だと商標登録といったことが多かったかと思いますけど、今は足立さんのような知財のマネージャーがおられるケースも多いですね。
じゃあこの3つはどう関係するの?ということになるんですけど、この3つの視点というのが、必ずしもいつもハーモニーを持っているとは限らなくて、結構コンフリクトを呼ぶ場合があると思うんですね。 今日はこのコンフリクトが起きたときに、どう解決すればいいんだろう、お互いがお互いをどう理解すればいいんだろうというところを聞いてみたいですね。
足立氏:私が所属している日本商標協会の中に、企業の知財担当者や弁護士・弁理士、知財関係の学者の人たちが集まるブランドマネジメント委員会というのがあって、そこでも知財の面からブランドってどう見たらいのか、といろいろ検討しあっているんですが、そもそも誰が一番最初に、ブランドという言葉を言い出したかははっきりしないまでも、アーカーやコトラーの言うブランドというものの定義が、全米のマーケティング協会の定義を用いていて、それはほとんどが商標、トレードマークの定義と同じなんですね。
それであるが故に、ブランドを担当している企業のメンバーも、知財の側の人も、「ブランド=商標」というのがなんとなく、一般的というか共通の理解になっていて、ただし実は本当にそうなのか?というところで混乱している。
 例えば製品だと、どんなものであってもネーミングが付けばそれはブランドである、という解釈に基づいて、小さなネーミングについてまで、これはブランドだ、このブランドはどうする、あのブランドをどうすると言っている。他方で経営側では、企業ブランドという側面でブランドの話がされていると。
例えば製品だと、どんなものであってもネーミングが付けばそれはブランドである、という解釈に基づいて、小さなネーミングについてまで、これはブランドだ、このブランドはどうする、あのブランドをどうすると言っている。他方で経営側では、企業ブランドという側面でブランドの話がされていると。
ブランドを一言で言うときに、一つの企業の中であってすら、そのブランドがなんであるかということは、必ずしも共通の理解になっていないケースが案外あって、それがコンフリクトの根源というか、スタートの一つかなという気がするんですよね。
つまりブランドによって、企業にとっても消費者にとっても社会にとっても、何かしらの価値がもたらせるのだ、ということが一番の中心になるんですけど、ブランドのエッセンスというものが多様な捉え方の中で曖昧になっているという。
ブランドというものはいったい何なのかを明確にすることで初めてコンセンサスを得て、企業の中での共通の取り組みができるんですね。
田中氏: 確かにブランドって何?ということが、いつまで経ってもずっと議論されているんですね。そこで経営とマーケティングと知財、この三角形と、ブランドの在りかたとを対照させて考えると良いと思うんです。
これは私の整理の仕方なんですけど、経営に該当するブランドというのは多くの場合、社会的にシェアされた知識によるもの。例えば三菱ってブランドはこうだよね、三井ってブランドはこうだよねといった、共通の認識として社会的に文化の中でシェアされた概念としてのブランド。
また、マーケティングに該当するブランドとは何かというと、商品に対する消費者個人個人の視覚などの知覚システムとしてのブランド。これは極端に言うと、ロゴやマークなしに成り立つものなんですね。
例えばレゴというおもちゃの場合、赤や青のブロックが店頭にあったとすると、多くの人がそれを見ただけで「あ、これはレゴだ。これは教育に良いおもちゃだから、うちの子供に買いたい」と思う。知覚システムとしてのブランドというのはこういうことを意味しています。
僕の考えているマーケティングのブランドってこの部分なんですね。消費者が反応する、或いは反応できるという一種の視覚のシステムが個人個人の中で生きている。
一方知財に該当するブランドとは何かというと、足立さんが仰ったようにアメリカのマーケティング協会が出している定義にある、マークとかトレードマークなどの記号としてのブランド。そして、これら3種類のブランドがお互いに緊密な関係でからみあって存在していることは間違いないのですが。
 陶山: 錯綜していると。
陶山: 錯綜していると。田中氏: ええ、錯綜しているんですね。それが故に問題が起きるということは充分有りうる。特にデザイン担当者と知財担当者の間のコンフリクトというケース。
田中氏: あるんですね。デザイナーはこのマークって今までこう使ってるけど、今回はちょっとこう変えたほうが良いんじゃない?みたいなアイデアを出したとしますよね。
それを知財の人からするともう、とんでもないことで(笑)うちのこの貴重なロゴに手を加えてどうするんじゃい、ということになるんです。それが消費者の知覚システムに働きかけるマーケティングの担当者の立場と、ブランドの価値の定義をしていくところの知財担当者とのコンフリクトの一つなんですね。そういう例はたくさんある。
足立氏: まあ、確かにその辺は、ブランドというものをどう捉えているか、ということによると思うんですけど(笑)ブランドというものは変化し得るものなんだ、ということについては、知財の人間も理解していると思うんですね。でもそれが企業として、きちんとした意思決定に基づいての変更なのか、ということなんです。
デザインや製品のある担当者が、「今回はこうしたいから」となると、いやいや、今までそのブランドをそれなりに何年もやってきてる中で、いったいどう考えてるんだ、その位置づけはどうなんだとなりますよね。それは企業としての戦略に基づいたものかどうかの議論もないままに、「自分がこうしたいから」では、ちょっと待ってくれよ、という話はどうしてもしたくなってしまう。 
それと費用の面でも、ちょっとロゴを変えてそれをまた登録するのかい?と。それって莫大な費用が掛かるんだよ、という話になるんですよ。なのでブランドを言葉でどう定義するかというより、何のことかを特定する企業もあるんですね。
例えば、社名のロゴとメジャーな製品名の2つだけがうちのブランドです、それ以外は製品のネーミングに過ぎません、と割り切って決めている企業もありますし、ブランドってそれこそ誰が言うかによって、何を意味しているかがバラバラだから、あえてブランドという言葉を使わないで、何のことを言っているかを特定して話をするという企業もあります。
私の所属している会社のように、コーヒーだったら「ジョージア」です、炭酸だったら「コカ・コーラ」「ファンタ」「スプライト」です、というように、もう製品の名前は全部製品ブランドだという企業もあります。
足立氏: 「コカ・コーラ」というのは製品ブランドに過ぎません。コーポレートブランドという考え方は基本的には無いです。
足立氏: ええ。会社名はザ コカ・コーラ カンパニーですが、考え方としてはブランドは製品に付されるものであって、それに基づいて会社の価値が高まっていると考えています。アメリカの本社からもコーポレートとしてどうだという話は基本的になくて、製品「コカ・コーラ」の話、製品「ジョージア」の話ということなんです。
足立氏: ある時期日本では、コーポレートブランドっぽいことを言い出したこともあるんですけど(笑)。今は基本的にないですね。ですからやっぱりそれぞれの企業の中で、自分のブランドはこれとこれ。あとはネーミングだと割り切ってしまうことも一つの方法なんじゃないかなと思うんですね。
そうすると、ブランドとは何であるかが企業内で明確になるので、ネーミングであればロゴを多少変えたって良いじゃないか、という話になりますし、そこの共通項ができるかなと。何年かブランドマネジメント委員会で検討してきて、そういうこともあるかなと、中間的な結論として出てきているところです。
 田中氏: 消費者の方からすると、そのブランドについて固定的に捉えている面もありますが、ある面では柔軟というか非常にクリエイティブになる場合もあるんですね。
田中氏: 消費者の方からすると、そのブランドについて固定的に捉えている面もありますが、ある面では柔軟というか非常にクリエイティブになる場合もあるんですね。
例えば「午後の紅茶」って女子高生なんかは「午後ティー」と言ったりするような。そういうのは「コンシューマー・ジェネレイティッド・ブランド」と言ったりしてるんですが、消費者側が勝手に作り変えてブランド化する場合もある。
また、ある企業がブランドを買って、トップマネジメントが「オレはブランドオーナーだから」と突然ロゴを作り変えてしまったという話もありますね。そういった場合は知財側がどう説得するか、抵抗するかという課題になりますが。
足立氏: まあ課題といえばそうなんだけど、例外もあるんじゃないかと思うんですね。以前、東京都下水道局のユニフォームにつけるワッペンが、内規と違うという理由で作り直しを命じて、たしか3500万円くらいお金をかけたという話がありましたね。
田中氏: ああ、石原都知事の。
足立氏: そうです。で、石原さんが「なにバカなことやらせてんだ」と言ったという事件がありましたけど、そういうのはそもそも行政の下水道局のようなところが、ブランドの話をすべきなのかという話と、それを誰のお金でマネージしてるんだっていうことですよね。下水道局のユニフォームのワッペンが少し違っていて、何の問題が起きるのかという。
何を守るべきなのかというところがはっきりしていれば、例外を認めることについてそんなに問題は起きないと思うんですね。それがはっきりしないがために、フォントだとかサイズだとか色だとか、といった形を守ることに囚われてしまう。
で、形さえ守っていれば良いとなって、そのブランドが伝えようとしているものが何であるか、実は汚されていても仕方ない、といった判断をしてしまっているケースがある。それは実は知財だけの問題ではなくて、ブランドマネージャーがしっかりコントロールできていないところにあるんじゃないかなと思うんです。
 田中氏: そこにキーワードが出てくるんですが、「ブランドダイリューション」希釈化ですね。知財では重要なキーワードですが、実はマーケティングの人はあまり考えていないんですけど(笑)
田中氏: そこにキーワードが出てくるんですが、「ブランドダイリューション」希釈化ですね。知財では重要なキーワードですが、実はマーケティングの人はあまり考えていないんですけど(笑)
その希釈化の話は足立さんに聞くのが一番ベストと思うので、そのジャッジメントはどのように采配されていたりするものなんですか?
足立氏: 希釈化と言う場合の一つに、自社での使い方によるものがあります。このブランド名はこういう人たちに向けて、こういうバリューを提供するものだ、と決めて使っていたはずなのに、その製品が売れているからと、いつのまにか別のもの、ひょっとしたら全然違うんじゃないの?というような製品にまで、同じような名前をつけたり、兄弟ブランド的に繋がろうとすることが、悪い希釈化の一つになります。
あとスポンサーシップの場合も、そのブランドにふさわしいところだと良いんですけど・・。
足立氏: ええ。そのブランドが伝えようとする価値とはコンフリクトが起きた、コンフューズドメッセージを提供してるんじゃないの?ということもありますね。それが自社使用での希釈化。
もうひとつは他社が冒用するような場合。第三者が全く別の製品に勝手に使っていて、あたかも同じ会社が出しているかのように見える。それが第三者による希釈化行為になります。
それはいわば、本来こういうものに限定して守るべきである、ということなのか、いやどんどんやっていいのかという、そこのスタンスはやはり、どちらが正しいか正しくないか、ということではないと思いますね。両方あるような気がします。
足立氏: 私も両方だと思います。それは両方なきゃいけないですね。
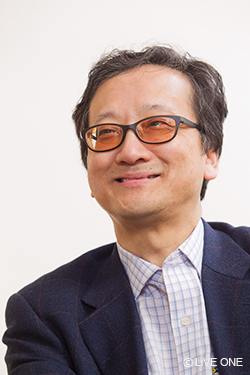 田中氏: そこにしくみが必要なんだと思いますね。マーケティングの側では、ブランドを付ければ売れるからって、なんでもかんでも付けちゃうってよくありますよ。売れる・ヒットするといえばもう錦の御旗みたいになる。
田中氏: そこにしくみが必要なんだと思いますね。マーケティングの側では、ブランドを付ければ売れるからって、なんでもかんでも付けちゃうってよくありますよ。売れる・ヒットするといえばもう錦の御旗みたいになる。
でも一方知財の側にすると、それはあまり快く思っていなくて、そこでコンフリクトになる。ただ、この間のやり取りって埒があかないので、やはりトップがここに介入して、これはいいけど、これはダメというルールなり、監督することが解決になると思うんです。
足立氏: 企業内でブランド使用委員会のようなものを作って、経営層や広報が入って議論している企業もあるんですけどね。最初は良いんですけど、それがだいたい経営層は多忙だから、と出なくなる。そうするといつのまにか形骸化して、また元にも戻って一対一でぶつかってしまう。
企業のしくみにもよるんですが、ブランドで生きて行くと決めた企業では、製品ごとにブランドマネージャーがいて、ブランドマネージャー間できちんと話し合われてるんですね。そういうところではいつも知財や法務の人間が入っている必要はないんです。
足立氏: ええ。知財や法務はそもそも、権利を獲るかどうするかという話なんですけど、いつのまにか、マーケティングの人たちが融通無碍に動きたがって、それを制御するのが知財や法務の人間だ、となってしまっているんですね。
田中氏: あとブランドマネジメントを担当するCBO(チーフ・ブランド・オフィサー)や、ブランドエクイティマネージャーをおいて管理するという話は、外資系ではよく聞くんですけど、恐らく日本の企業は、個人個人に権限委譲があまりされていない場合が多く、うまくワークしていないように思います。マーケティングにもブランドにも、やっぱりリーガルのことについても見識がないといけないですから、実際にはこうした専門マネージャーを設置する管理の仕方はなかなか難しいんでしょうね。
 陶山: 知財・マーケ・経営とそれぞれが現場で、三位一体としてやっていかないといけない、ということはもちろんなんですけど、やっぱり経営トップがまず、三位一体の存在意義や役割りをきちんと認識して、全社的なムーブメントにしてくことが必要でしょうね。
陶山: 知財・マーケ・経営とそれぞれが現場で、三位一体としてやっていかないといけない、ということはもちろんなんですけど、やっぱり経営トップがまず、三位一体の存在意義や役割りをきちんと認識して、全社的なムーブメントにしてくことが必要でしょうね。やはり現場のところで動きをつくろうにも、ブランドというものの理解や認識が、全社的に浸透されていないとなかなか動きづらい。各部門ごとの部門最適はできても、ブランドという名の元で動いて良いよ、というトップのお墨付きがないとGOがかからないんです。
足立氏:ブランドマネージャーの権限委譲がきちんとできている、或いはこのブランドはこういうことなんだ、と全社的に浸透させておくことだと思うんです。そうすると大きな方針は出ているわけですから、それに基づいた動きにしかなっていかない。
それに大きく反するような例外的な場合にはじめて、トップにどうすればよいか話ができると、そういう形になっていれば現場は動くと思うんです。
田中氏:根本的には企業の組織の一人一人が、ブランド価値を意思決定の基準にする、ということがすごく大事だと思います。意思決定の基準とするというのはつまり、このアクションをすると、ブランド価値が高まるよということ。
通常マーケティングや営業だと、このアクションすると売上が上がる、という売上を優先しちゃいますよね、きっと。だけどそこを、売上も上がらなきゃいけないけど、ブランド価値も高めなきゃいけない、という判断が、組織のそれぞれのメンバーにあるかどうかなんです。じゃあどうするかということなんですけど、昔僕は「ブランド・ドリブン・マネジメント」とう言葉を自分で勝手に作って言ってたんですね。
陶山: ああ、マーケット・ドリブンとかありましたね。
田中氏:ええ、そんな感じです。何をイメージしていたかというと、レギュレーションというか規則をカチっと作るんです。昔十数年ほど前ジャガーに行った時に、彼らはそれをずっと一生懸命にやってるんですよ。ジャガーブランドというのはこういう価値だからこういう規定だと。

そこからインテリアはどうするとか、環境対策はどうするとか議論される。どこの属性に力をいれたら良いかという、非常に体系的でシステマティックなんですけど、ただ逆にそれは非常に固い体系なんですね。
それで最近僕は、「ブランド・ドリブン・マネジメント」ではなく、「ブランド・インスパイアード・マネジメント」ってでっちあげて言ってるんです(笑)
陶山: (笑)
足立氏:(笑)
田中氏: これは何をイメージしているかというと、たとえばGoogleだと、「僕はGoogleに勤めているから、こういう使命があってこういうミッションがある。だから僕はこうしなければいけないんだ」という、ブランドからの教えがあって、行うことが自ずからブランドになっている。
それがぼくの言う「ブランド・インスパイアード・マネジメント」なんです。必ずしもマトリクスを書いて、ガチガチにやらなくても良いんじゃないかと。そういうしくみを組織の中にビルトインする。それが理想なんじゃないかと思うんです。
陶山: ユーザーから見た評価を上げるためにはブランドビルディング、基本的なベースからだんだんパーソナリティまで上がって、シンボルまで行かなければいけない。でもそれってかなり疲れるでしょうと。
ある食品メーカーで、以前はPB商品など開発もされていたんですが、数年前から売上至上主義になって、とにかく利益を出さないといけない、ということになった。何が変わったのかと聞くと、経営トップが替わって、ステートメントが変わったからって言うんですよ。つまり評価軸が変わったと。経営トップと現場がインスパイアされるようなカルチャーを、どう作っていくかというのはなかなか難しいですね。
 足立氏:トップマネジメントの方も、やっぱり売上や利益は、株主のことを考えると、目標として達成しなくちゃいけないものとして出てくる。そうするとブランドというのは、言ってみれば事業していく上でのツールだったりするので、目標を達成するのために、今あるブランドをなんとか使う、という話は出てきかねない、というか有り得る話なんですね。
足立氏:トップマネジメントの方も、やっぱり売上や利益は、株主のことを考えると、目標として達成しなくちゃいけないものとして出てくる。そうするとブランドというのは、言ってみれば事業していく上でのツールだったりするので、目標を達成するのために、今あるブランドをなんとか使う、という話は出てきかねない、というか有り得る話なんですね。
ブランドインスパイアということでみると、従業員もそうですが、実はマネジメント自身が、ブランドとはこういうことなんだから、ちょっと市場が変わって短期的な売上が必要かもしれないけど、ウチとしてはこうなんだ、この範囲は絶対踏み出さないんだ、ということがきちんと示されていれば、経営者が変わろうが変わらなかろうが、脈々とそれが生き続いていく。
そういうことがないといけないんだろうなと思いますね。といっても、やはり経営をしていかないといけない人たちなので、難しいでしょうけれど。
田中氏:日本の企業の経営者は、ブランドを活用した経営の旨みをまだ知らないんですよ。海外の企業の経営者だと、ブランドをやるとこんなに良いことがあるということが、骨身に沁みてわかってる。日産のゴーン氏もそうですし、P&Gの元CEO、AGラフリー氏もね。
彼らは骨身に沁みてブランドが如何に大事だということがわかってて、だからこそブランドを中心にした経営をしなくてはいけない、ということを当たり前のようにやっている。
でも日本の企業の経営者はそこまで経験していない。まあ経験がないということは、ある意味すごく幸せなことなんですけどね。経営が安定していれば、あまりブランドということを考えなくても、なんとか営業力でやっていけるけれど、一旦左前になったときに、ブランドの力を使って再構築する。そういう経験があるかないかだと思うんですね。
ある家電メーカーも今大変な状況で、「破壊と創造」といってかなりドラスティックにされていますが、コストカットといった部分よりもっと、コンストラクティブな動きをどうするかというところに、ブランディングが力を発揮すると思いますね。
 田中氏:企業のDNAというかブランドの歴史の、いわば再解釈することも一つあると思うんですね。つまりうちのブランドは、こういう歴史を経て、こうなったブランドなんだと。歴史にはいろんな事が起きているので、如何ようにも解釈できるわけです。
田中氏:企業のDNAというかブランドの歴史の、いわば再解釈することも一つあると思うんですね。つまりうちのブランドは、こういう歴史を経て、こうなったブランドなんだと。歴史にはいろんな事が起きているので、如何ようにも解釈できるわけです。
過去にはこういうイベントがあってこうだったという。だからこのブランドはこういう価値を持ってて、こうしなくちゃいけないんだと、その歴史の中から出てくるプロセスですね。これをまず、経営者自ら考えていく必要があると思いますね。
ゴーン氏の説得の仕方って、非常にシンプルなんですね。うちの車は数万円しか安くできない。だからブランドをやならければいけないと。それは誰でもわかる理屈ですね。そういうシンプルな理屈を考えて、それをもう繰り返し、繰り返し、繰り返し。ゴーン氏は今も同じことを仰ってます。
でも日本の経営者には、「オレが1回言やぁ、わかるだろう」と思ってる人って結構多い(笑)人間ってずっと同じことを言わないと、なかなか変わる事ができない。繰り返すことって大事かなあと思うんですけどね。
足立氏:やっぱりブランドについては、きちんとディスカッションすることだと思うんです。新しい製品に名前をつけるとか、あるいはロゴを変更しようとかいうときに、ブランドマネージャーやマーケティングのマネージャー、知財のマネージャーが話し合いをした結果、じゃあこうしようと進んでいくことが必要ですね。
誰かが言ったから、それに皆従わないといけない、というのあまり良くないと思うんです。ディスカッションをすると、それぞれが気付いていなかったこともわかって、少しやり方が変わっても全員が頂点に向かっていける。
そうでないと、知財の人間にすると「言うこと聞いてくれない」と不満になったり、マーケティングの人たちからすると「知財・法務の人間はうるさく言ってくる」と(笑) お互いに不満だけ持ってて、実は生産的になってないということが少なくない気がするんですよね。
やっぱり話をするとなると、そりゃ不愉快な思いをするかもしれないし、100%それぞれの思惑通りにはならないかもしれないけど、会社の方向としての話をすることができる。そこが企業として、ブランドを使って事業していく上で大切なことなんですけどね。
わが社の基本的な歴史や考え方で行くと、取るべき戦略という具体的な商品開発のありようはこうだと仰るんですね。現場においても、自社のミッションや伝統や歴史をブランディングの視点に踏まえて、自分たちの心棒を持っていて、そこは全くブレないという。これがまさに必要なんです。
 足立氏:ブランドの世界から見て、企業ブランドやコーポレートブランドという考え方というのは、日本特有のものなんですかね。それとも他の国でもわりと一般的にあるものなんですか?
足立氏:ブランドの世界から見て、企業ブランドやコーポレートブランドという考え方というのは、日本特有のものなんですかね。それとも他の国でもわりと一般的にあるものなんですか?
というのが、私が思うに企業の価値は、製品ブランドなりサービスブランドの結果として上がっていく、そんなイメージを持っているんですが、最近日本のいろんな企業の方たちと話していると、コーポレートブランドということが先に出てくる。
どういうイメージを提供するかというコンセプトからネーミングが出てくる、というより先に企業名があって、企業自体にこういうイメージを持ってもらいたい、そのためにどうするか、ということを話されていることが多いんですね。
それが私にはやはり不思議なように思うんですけど、実際はどんな感じなんですか?
田中氏:僕はコーポレートブランドを考えるのは、日本特有だとは思っていないんですが、ただ、コーポレートブランドの捉え方には、日本特有の特徴があると思います。
足立氏:そんな気がしますよね。
田中氏:一つに日本は商品ブランドがあまり発達していない、ということがあるのかもしれないですね。P&Gのようにワンビリオンブランドを20以上も持ってるような企業って、日本にはないですから。
P&Gはもう比較できない規模だから、同じような真似はできない。そこでどうしてもコーポレートブランドを中心にして考える、ということになり易いんでしょう。もう一つ、「企業」というものが日本人にとって最も近しいというか。
足立氏:帰属の意識ですよね。そのイメージが強いんですかね、やっぱり。
田中氏:ええ。それもあると思いますね。
足立氏:そのせいか、インターナルブランディングとか、インナーブランディングといったことが、結構出てきていますよね。もちろんそれは必要だと思うんですけど、でも何か、ブランドは事業のもの、と私はどうしても捉えてしまうので、そこから捉えてしまうと、やや散漫になってしまわないのかな?という気がするんですけど。
田中氏:仰る通りですね。インターナルブランディングについて、なんやかんやと言いたくなるのも、日本の企業の社長さんの特長かと思います(笑)
 陶山: 今までのブランディングというと、広告といった対外的なコミュニケーションのためのツールや手段として理解されていた。それはそれでいいんだけど、社内の合意形成やビヘイビアを起こせるまでにはならないと。
陶山: 今までのブランディングというと、広告といった対外的なコミュニケーションのためのツールや手段として理解されていた。それはそれでいいんだけど、社内の合意形成やビヘイビアを起こせるまでにはならないと。トップがいくらブランディングと言っても、なかなか末端まで理解がいかない。それでまずは全社的に、ミッションやビジョンについてのブランドブックを作成して、と形から入っていくんです。でもそこからでないと全社的なブランド戦略に入っていかないということがあるんですね。
P&Gがシックと言うブランドをもっているのはM&Aなんですね。つまりすでに確立された製品ブランドがあって、それらの集合体としてP&Gがあり、LVMHがあるという。そこで欧米の場合、P&Gって何?LVMHって何?ってことはあまり考える必要がない。そういう成り立ちがあるからじゃないかと思います。
田中氏:そうですね。ブランドの体系の成り立ちがそもそも違いますね。買ったブランドが多いか、オーガニックブランド(自社で育てたブランド)が多いかということもありますね。
足立氏:アメリカ系企業はどちらかというと、プロダクトブランドでモノを考えていて、たまたま最初の製品名が企業の名前になっていることが多いんですね。GMもカンパニー制になっていて、必ずしもGMという名前がいつも付いてくるわけでもないですし。
足立氏:うーん、それはそうなんでしょうけれど、BMWにしてもメルセデスにしても、その企業名が付いてるんだけど、企業のことをイメージするかっていうよりは、車そのものをイメージすることが多いかと思うんですよね。消費者もどっちかというとそっちのイメージだし、売っている人たちも。日本の企業は「この企業が出しているこの商品」といった打ち出し方のほうが多いような気がして。それが日本特有なのかなと思ったりするんですけどね。
 陶山: 私が調査した際に、P&Gのシャンプーは製品機能が優れている、オシャレでかっこいいと。ところが日本の企業だと、男性の場合、花王の「メリット」?薄いグリーン色のパッケージのシャンプーでは?となります。つまりプロダクトブランドがあまり確立していないんですね。
陶山: 私が調査した際に、P&Gのシャンプーは製品機能が優れている、オシャレでかっこいいと。ところが日本の企業だと、男性の場合、花王の「メリット」?薄いグリーン色のパッケージのシャンプーでは?となります。つまりプロダクトブランドがあまり確立していないんですね。今はもう資生堂や花王ってあんまり関係ないやということに、少しづつなってきているんでしょう。そうした日本の企業のブランディングの歴史や、欧米企業との比較をふまえて、日本の企業にふさわしい調査と研究をしていかないといけないですね。
田中氏:実態の調査って大事だと思うんです。20年ほど前は日本の企業が注目されていましたが、今や日本の企業のマネジメントに関心ある人は誰もいない。だけどやっぱり、現実に日本の企業では、どんなマネジメントが行われているかの調査はやったほうが良いですね。
今中国もそうですけど東南アジアであったり、リージョナルな活動でのブランド戦略はどうあるべきかというのは必要ですから、グローバルブランドも研究しないといけないですね。
田中氏:日本企業が意外とグローバルブランドを持ってるということがありますね。メンソレータム(ロート製薬)、サーモス(サーモス株式会社)、ファーファ(日本のみNSファーファ・ジャパン)などです。M&A等で知らない間に売買されて、ブランドがその企業固有のものでなくなっていくこともあります。その後育っていたり無くなっていたり、いろんなことが起っていますから、そこをフォローしても面白いかなと。
足立氏:以前より目立たなくなってしまったブランドもありますよね。
田中氏:ええ、ブランドの売買によってブローする場合もありますしね。そんなプロセスを見ておくのも良いかなと。企業も合併したあとにどうなるかというのも大事な話で。
あと測定の問題ですね。メジャメントってこれもいろんな説というか、考え方が提案されていますけど、もうちょっと違う測定はないのかと思っています。ブランドの価値ってそのまま直接は測れないんですね。代理変数を用いて測定しないといけないと思うのですけど、どのような変数を用いたらうまく出てくるのか、というのはまだ空白になってる。
田中氏:いまどきブランドが大事じゃないという人はいないんですよ。だけどそれが何に結びついていくのかということですよね。アメリカのケラーによって、シェアホルダーバリュー、投資家とブランド価値がどう結びついているかという研究がもう行われていますから、日本でもそういった観点の研究もやっていくと良いでしょうね。

米国ニューヨーク州弁護士
日本コカ・コーラ(株)ディレクター&シニアリーガルカウンセル
兵庫県生まれ。米国イリノイ大学ロースクールLLM(修士)。1997年日本コカ・コーラ(株)入社。2005年より日本商標協会理事。2009年より日本商標協会常務理事 同協会ブランドマネジメント委員会委員長。2011年より、一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター理事。日本弁理士会研修委員会にて、「ブランド戦略」についての講師を務める。2012年12月より、日本弁理士会中央知的財産研究所会員外研究員。論文等:『最新判例からみる商標法の実務』(共著 青林書院, 2006)、「ブランドと稀釈化(ダイリューション)について」(日本商標協会誌64号 2007)、「Coke sets precedent in Japan」(共著、World Trademark Review issue 15, 2008)、「立体的形状のみから成る商標の登録」(Law & Technology42号, 2008)、『最新判例からみる商標法の実務II(2012)』(共編著 青林書院, 2012)、「企業におけるブランドマネジメント」(知財研フォーラム91号 2012)など。 学会等:日本工業所有権法学会、著作権法学会、日本マーケティング学会など。
田中 洋氏
中央大学大学院戦略経営研究科教授
京都大学博士(経済学)
1951年名古屋市生まれ。慶應義塾大学大学院後期博士課程単位修得。1975年(株)電通入社、同社マーケティング・ディレクターを経て、 1996年城西大学経済学部助教授、1998年法政大学経営学部教授、2003-4年度コロンビア大学大学院ビジネススクール客員研究員。この間、フランス国立ポンゼショセ工科大学ビジネススクール、東北大学、名古屋大学、慶應義塾大学、早稲田大学などで講師。経済産業省・内閣府・特許庁などで委員会座長・委員を務める。2008年 4月より現職。日本マーケティング学会(2012年11月設立、学会長 石井淳蔵神戸大学名誉教授・流通科学大学学長)副会長。マーケティング論専攻。消費者行動論・マーケティング戦略論・ブランド戦略論・広告論に関心。多くの企業でマーケティングやブランドに関する戦略アドバイザー・研修講師を勤める。その著作・研究活動により、日本広告学会賞を三度、また2008年度中央大学学術研究奨励賞を受賞している。翻訳サービスの(株)言コーポレーション顧問。日本マーケティング学会副会長。マーケティング論専攻。多くの企業でマーケティングやブランドに関する戦略アドバイザー・研修講師を勤める。日本広告学会賞を三度、また2008年度中央大学学術研究奨励賞、2012年白川忍賞などを受賞。主著に『ブランド戦略・ケースブック』(2012)、『マーケティング・リサーチ入門』(2010)、『大逆転のブランディング』(2010)、『消費者行動論体系』(2008)、『現代広告論』(2008)、『企業を高めるブランド戦略』(2003)など多数。
URL:http://hiroshi-tanaka.net/
取材:2013年