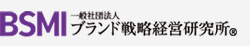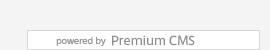HOME» ブランド対談 #02 »ブランドを立てる「MPDP」理論
ブランド対談 #02
ブランドを立てる「MPDP」理論
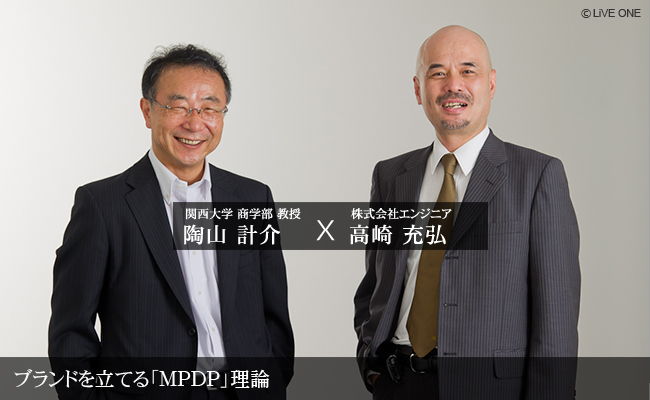
ブランドを立てる「MPDP」理論
代表取締役 高崎充弘氏
 陶山: 高崎社長は、お父さんの会社を継がれて自分の代になってから、オリジナルのものを作ろうとされたんですか?
陶山: 高崎社長は、お父さんの会社を継がれて自分の代になってから、オリジナルのものを作ろうとされたんですか?高崎氏:もともと創業時からファブレスで工具を作ってきた会社で、父親も自分で商品開発をしていたんですね。そこへ私が造船会社に約10年間務めていたんですけど、親の事業を継げということで帰ってきました。
それから自分の代になってから20数年間、約800アイテムの新製品を作ってきました。現在製品化しているものは小さな部品も合わせてですが、全部で1000アイテムあります。
高崎氏:ええ、その中で売れないので製造中止になったものもありますが。
高崎氏:ええ、増えていますね。
高崎氏:結構カルチャーショックはありましたね。前職の造船会社のように、きちんとシステム的に人が動いているのと違って、社員20名の会社ですから、「こんなことがまだ、こういうカタチなのか」と思いました。これは自分なりに変えていかなければと思いましたけど、基本的に人が動くわけですから、しくみだけパッと作ってもうまくいかない。
しくみの上で働いているのは人ですから、まず人を変えていかないといけない。大企業なら、まず組織のしくみに乗る人しか採用されてきませんから、指示を渡せばすぐ済みますが、そういう環境じゃないですし、また、言われたことを勘違いする人もいますから。やはり人を変えるというのは難しいですね。ようやく今25年たってカタチになってきたかなというところですね。
高崎氏:いえ、「MPDP」ができたのはごく最近で、いままでの失敗の経験の中から生まれたんです。ネジザウルスが最初に出来たのが2002年、大きいねじ用、小さいねじ用と3機種作っていたんですね。
リーマンショックの後、このままじゃいけないと思いまして、「一家に一本、ネジザウルス」を合言葉に、ご家庭でも使えるような4代目を作りました。 ぱっと見はあまり変わらないんですが、これが初代3機種を合計した数の倍近く売れたんです。
 そこで、なぜこんな売れたのか、これまでに開発した800アイテムには無くて、これにあるものは何か。
そこで、なぜこんな売れたのか、これまでに開発した800アイテムには無くて、これにあるものは何か。
よくコンサルタントの方々が「SWOT分析」をされますけれど、私は弱みをいまさら抽出しても意味がないと思い、ドラッカーの言葉に「強みの上に強みを築け」とあるように、強みだけを抽出していろいろ分析してみたんです。
つまり、この製品にはどんな強みがあるのかと考えると、お客様の声を聞いてマーケティング(Marketin)した、特許(Patent)もとった、デザイン(Design)も賞を取った。プロモーション(Promotion)もやった。だから売れた。
そこでそれらの頭文字をとって、売れた理由には「MPDP」があったという考えに至りました。
「子孫に井戸を与えるよりも、井戸の掘り方を教えたほうが良い」といいますよね。成功した理由が判れば次の製品開発に役立つと思ったんです。これで、このネジザウルスという製品を作ったことよりも、「MPDP」という考え方を見つけたほうが私には大きいですね。
ヒット商品が生まれた秘密を体系的に探るところが興味深い。普通はなかなかそこまで気付かないですから。また、その商品を開発するまでにいろんな経緯があったと思うんですが、なぜそれまでの開発がうまくいかなかったのかもお聞きしたいですね。800アイテムの商品開発をされてきた中で、今振り返ってみてなぜ大ヒットしなかったのか、どこに問題があったと思われますか?
高崎氏:「MPDP」が一つだけ足らなかったらどうなるかとか、1つだけしかなかったらどうなるか、ということも考えたことがあるんです。M(マーケティング)が無かったら、そもそも市場にニーズがない、ということですから、つまり「ワイシャツの最初のボタンを掛け間違っている」状態で、あとのPDPをやっても売れないんですね。まず出発点が間違っているわけですから 。
 P(パテント)が無い場合、2つの問題があって、一つは自社が開発しても、他社がパテントを先に取ってしまえば権利侵害と言われる。もう一つ、自社も他社もパテントを取らない場合、市場にはすぐ模倣品が出回ってしまう。いずれにせよ長続きしなくなる。
P(パテント)が無い場合、2つの問題があって、一つは自社が開発しても、他社がパテントを先に取ってしまえば権利侵害と言われる。もう一つ、自社も他社もパテントを取らない場合、市場にはすぐ模倣品が出回ってしまう。いずれにせよ長続きしなくなる。
D(デザイン)が無い場合、消費者の立場で考えてみて、同じ機能で同じ値段だったら、やっぱりデザインの良いほうを買いますね。あと、P(プロモーション)が無い場合は、営業戦略が無いということですから、MPDまで3つ揃っていながら非常に惜しい。最初の出だしは良くても、途中で必ずブレーキがかかってしまいます。
私がこれまで開発してきた800のアイテムやネジザウルスの初期3機種は、「MPDP」が全て揃っていないまま勝負しようとしていたことが売れない理由だったと思っています。
高崎氏:ええ。たとえば、「お客さんからこんなものが欲しいという声があるのに売れない」「こういう特許取ったのに売れない」といったことですね。特許取ることにしても、特許を取る=特許を取れたほどの優秀な製品だ、と勘違いして、「なぜ売れないんだろう」と悩んでいる方はたくさんおられます。
特許は登録の範囲を狭くすれば100%近く取れますし、今までに無い斬新な色やデザインにしたら売れるかといえばそうじゃない。また宣伝や広告をすれば売れると思い込んでいても売れませんよね。800もの試行錯誤をして生まれたのが「MPDP」なんです。
でもその800アイテムも、やはり20年も開発の経験があるわけですから、「これは絶対売れるぞ」「これはすごいぞ」「きっと大ヒットするぞ」と、どれもそう思って開発してきたんですよ。
高崎氏:ええ。なのになぜ売れないんだろう、こんなはずないのにとずっと悩んでいましたね。
市場のニーズに、どこが一番核心なのか、誰が重要なのか、そこを突破して新しいものを生み出そうとされた経営トップやマーケターのセンスがヒットの大きな要因じゃないかと思いますね。ある意味マニアックとも思えるニーズに注目されたところが面白い。
 高崎氏:そうですね。初期のネジザウルス3機種に「愛用者カード」というアンケート用紙を入れていたんですね。30-40万個くらい売った中から、1000枚ほど返って来ていたんです。
高崎氏:そうですね。初期のネジザウルス3機種に「愛用者カード」というアンケート用紙を入れていたんですね。30-40万個くらい売った中から、1000枚ほど返って来ていたんです。
その中に記載されたお客様の要望を、多いものから順番に並べてみて「トラスねじが外せたらいい」というのは5番目くらいでしたね。非常に少人数の要望だったんです。
社内で開発会議して、「トラスねじって、そうだよね。外したいよね」って話はしていたんですが、少ない人数しか要望していないことを盛り込んでも・・って悩みましたね。どこで線を引くか。
まあ、この形状ってそんなにコストがかかることでもないし、ちょっとしたことでできるんだから、やってみようということになったんです。
3次元CADで作ってみて、先端をこういう形状にすればできると検証して、実際に試作品を作ってみたら確かにトラスねじも外せるんですね。
この時に2つ目の発明考案が誕生したのです。弊社で「コマネチ特許」って呼んでいる(笑)最初の特許に続く2つ目の特許です。しかし、最初は売れるかどうか不安でしたね。ここに何をどこまで盛り込めば売れるかと考えましたが、そんなにコストをかける体力もありませんでしたし、最低必要な機能だけ盛り込んだんです。
高崎氏:まあ、お客様は「トラスねじを外したい」と要望するだけで、どうしたら良いかは言ってくれないですからね。
ものづくりの企業となると、マーケティング的ではなかったり、プロモーションやデザインを考えることが少ないと言われていますが、そうではなく、徹底的に「ものづくり」にこだわるなかで、同時にマーケティングやデザイン、パテントを取るといった市場を「見通す力」も生まれます。これがものづくりのメーカーとしての一つのエッセンスではないでしょうか。そのとき大事なのはモノの形だけにこだわらないで、その価値を考えることでしょうね。
高崎氏:「見通す」ということって大事だと思いますね。ものづくりの企業は作ってなんぼで、あとは誰かが売ってくれるだろうではなくて、消費者の手元に届いて満足感を与えるためには、こういうデザインでなければとか、心に触れるプロモーションは何かといった、川上から川下まで完結した見通せたものづくりをしないと、途中でぶちっと切れるようなビジネスではだめだと思います。
特許を取っても、それは一つのプロセスとしての流れの中にあるだけで、やはり最後まで「MPDP」という一環したものが必要だと思います。
 陶山: 御社はチームエンジニアと呼ばれている社員30名。高崎社長のリーダーシップが社員の中に浸透していくには、比較的やりやすい環境だったのでしょうね。
陶山: 御社はチームエンジニアと呼ばれている社員30名。高崎社長のリーダーシップが社員の中に浸透していくには、比較的やりやすい環境だったのでしょうね。大企業のように多くの部門があって、巨大化すれば意思決定するのに時間もかかり、経営トップから現場まで、開発から営業まで見通せないといった難しいところもあります。そういう点では、御社は企業がフレキシブルかつダイナミックに機能する条件が揃っていたのではないかと思いますが。
高崎氏:ええ。小さい組織だからできたのもあります。
以前アメリカでネジザウルスの販売を展開しようとした際に、現地の取引先の方に、「アメリカの企業は2,3年で急成長することがあるが、それはなぜか判るか」と聞かれたことがあります。
聞くとアメリカでは社内社外関係なく、あるいは国境もなく、一つのプロジェクトに専門家たちが集まってミッションを完結するからなんだそうです。
あるシーズがあるとしたら、それをどう育てるか専門家が集まってくる。そしてそれが終われば皆、それぞれ別のプロジェクトへと去っていく。あの映画の「オーシャンズ11」のようなものですね。
片や日本の企業はせいぜい部門横断型プロジェクト。人材の流動性の違いですね。とはいえマーケティングもデザイン、パテント、プロモーションとそれぞれを分けてしまったら、絶対だめだと思うんですね。そこにはまとめ役のリーダーが必要になりますし、中小企業もそういった本当のプロ達が揃えば、もっと面白くなるのにと思うんです。
高崎氏:経営トップでなくても、社内にプロジェクトマネージャーという人が必要ですね。少しづつでも良いから全体を理解している人が。私も図面は社員に負けるし、プロモーションも社員に任せてますし、オールマイティというわけじゃないんですよ。唯一ネーミングだけが私ですが(笑)
 陶山: なるほど(笑) ネジザウルスというネーミングも?
陶山: なるほど(笑) ネジザウルスというネーミングも?高崎氏: ネジザウルスの名前は社内で公募しました。公募して即決でしたね。デザインは社員がしてGoodデザイン賞も頂いたんですが、その授賞式の場で、今後はプロのデザイナーにお願いしなくてはと思いました。
その後は、プロのデザイナーにアドバイスをいただいたり、パテントは弁理士の先生にお願いし、プロモーションもと、それぞれの専門家へアウトソースしています。今は社員が専門家の方々の窓口として機能するようになってきました。
高崎氏: ええ。あのApple社もいわゆるファブレスなんですね。マーケティング、デザイン、パテントも。プロモーションはジョブス社長が自らされてましたけど。今のものづくりの業界も、他の中小企業と連携しながらのアウトソーシングという方式は充分成り立つと思います。
たとえばネジザウルスが100万本売れたということは、その中に使われているネジも100万個売れたということになります。樹脂成型屋さんも100万個分の注文が入っているわけです。 今大企業の工場が中国やミャンマーなどに移転して行く中で、どんどん仕事も無くなり空洞化してきていますけど、私どものような会社がたくさん出てくると、ものづくりの裾野も活かせるんじゃないかと思いますね。
父親の代はまだそこまで考えていない時代でしたが、今の時代、早くしないとそうした中小のものづくりの会社自身、後継者も無くどんどん減ってきています。そうなるとますます日本の体力もなくなってしまうんです。
私の言う「MPDP」も、私が日本人だから言えること。韓国や中国で「MPDP」って言っても、「じゃあどこの工場で作るの?」という話になりますから。
日本という国にいるからこそ、「MPDP」という考え方を持てば、ちゃんと精密な良い製品ができる素地がある。
 ただ、どう形にして、どう売って利益を出していくかのプロセスがないんだと思いますね。よくマーケティングの話で、4Pとか4Cとか言いますね。でも私の「MPDP」には2つのPがありますが、プライスとプロダクトは入ってないんです。
ただ、どう形にして、どう売って利益を出していくかのプロセスがないんだと思いますね。よくマーケティングの話で、4Pとか4Cとか言いますね。でも私の「MPDP」には2つのPがありますが、プライスとプロダクトは入ってないんです。
高いと売れないから適正価格を出すということも、良いものを作らないと売れないということも、それは誰でもご存知のことですから。
高崎氏:あっブランドですね(笑)。
以前先生にそう言われて考えたんですが、私がネジザウルスを作ったから言うんじゃないですけど、「MPDP」って2重螺旋のイメージかなと思うんです。土の中をぐっぐっとドリルで掘っていくような。
その掘削ドリルを経営トップが回して、ぐぐっと回せば回すほどブランドができてくる。ブランドができれば価格競争にならなくて済む。つまり「MPDP」がブランドを作るツールになるんじゃないかと思ってるんです。これからは中小企業もブランドを作らなければいけない。
企業のオペレーションを担当されている方に、もっとブランドマネジメントを考えて欲しいんですね。その点で「MPDP」は、ブランドを立てるのに役立つ考えになりますね。
やはりこれからはICT革命(情報コミュニケーション技術革命)のもとでグローバル競争がますます進みますが、今のままだとその中でどんどん埋没していってしまいます。その厳しい環境の中でブランドを立てるためには、如何にして尖がった企業イメージや製品ブランドを出していくか、が大きなテーマになってきます。
そのブランドを立てるための4つのステップを「MPDP」であると考えると、その4つのステップを支える「縁の下の力持ち」が経営トップのリーダーシップです。
 高崎氏:今弊社は「エンジニア」という社名よりも「ネジザウルス」のほうが有名になって、コーポレートブランドよりプロダクトブランドのほうが大きい状態ですね。
高崎氏:今弊社は「エンジニア」という社名よりも「ネジザウルス」のほうが有名になって、コーポレートブランドよりプロダクトブランドのほうが大きい状態ですね。
でも最近はネジザウルスというブランドに引っ張られてか、コーポレートブランドも上がってきてるような気がします。
ネジザウルスが載ってるエンジニアさんのカタログが欲しいといった声もいただくようになりましたから。やっぱりブランドって製品と繋がってるんだなと感じます。
そこから、そのシルバーブリットに負けない「エンジニア」というコーポレートブランドを、どう立てていくかが今後の課題になるでしょうね。やはり会社である以上、製品の他にも、社員や経営トップの「人としてのブランド」など、トータルで見た企業のブランド価値を上げることも必要ですから。
高崎氏:この企業といえばこの製品だとわかるようなことですね。次に出す商品も、非常に強い弾丸でなければいけないということですね。
高崎氏: 何か1つプロダクトブランドがあればいいというわけじゃないんですね。製品ブランドとコーポレートブランド、両方必要になる。
高崎氏: そうなんですね。
 陶山: ええ。松下は「パナソニック」とラインブランドの名前に社名を変えましたね。グローバルで強いブランド名に社名を変更するのも一つの選択ですけどね。
陶山: ええ。松下は「パナソニック」とラインブランドの名前に社名を変えましたね。グローバルで強いブランド名に社名を変更するのも一つの選択ですけどね。高崎氏: 株式会社ネジザウルスとか(笑)
高崎氏: そうですね(笑) 弊社は、クールでイノベーティブな機能・デザイン・遊び心、この3つを持った工具メーカーとして世界に売っていこうというミッションを持っているんです。
そこにコーポレートブランドをどう立てるかと考えると、ネジザウルスって、クールでイノベーティブな製品だよね、ちょっと遊び心もあるし。じゃあ、そのネジザウルスを作ったエンジニアって会社なら、次はきっとこんな感じの製品を出してくるだろうな、とイメージしてもらえることが大事なんですね。
高崎氏: あの大きな企業でも人がブランドなんですね。
高崎氏: トップがブランド力を持つことって日本でなかなかいないですね。大企業でも少ない。
 高崎氏: 僕は、企業が打ち出すミッションってその企業のブランドイメージですから、経営者自身のイメージと商品イメージは合っていたほうが良いんじゃないかと思うんですね。社長のキャラクターと想いがそのまま製品に反映するといったような。
高崎氏: 僕は、企業が打ち出すミッションってその企業のブランドイメージですから、経営者自身のイメージと商品イメージは合っていたほうが良いんじゃないかと思うんですね。社長のキャラクターと想いがそのまま製品に反映するといったような。
逆にいうと、企業や製品だと形になりますから、そこにポテンシャルがあまりないんですね。つまり伸びしろがない。人であればどんどん成長し続ける存在ですから、次々と新しいアイデアやビジョンが生まれてくる。そういう意味では、経営トップのブランド力を上げることが会社の成長を一番後押しするものになるのかもしれません。
経営トップがイノベーティブでクリエイティブな考え方をしなくなると、いわゆる大企業病といわれるような、面白くともなんともない金太郎アメのようになって、新しいものがなかなか出てこない。いわゆる硬直した企業風土になってしまいます。
経営トップ自らが常にカオスのような状態を作りながら、何かやってくれるんじゃないかと周りへの期待感を作り上げること。ブランドとは、期待と満足を取り結ぶものですが、単なる期待だけでなくて、期待以上のものを提供してくれるという「驚き」がないとヒット商品に繋がらないんですね。
日清のカップヌードルのような全く新しいもの、パラダイムシフトを起こすことによって、常になにかやってくれるという期待感が生まれてきます。
高崎氏: なるほど。ところで、陶山先生のブランド戦略経営研究所の会員企業には、中小企業の方もおられますか?
 この点ではブランド戦略経営研究所の会員でもあるメーカー、流通とかの比較的大きな企業や、調査企業、広告代理店などでは、ブランドやコミュニケーションということをよく考えておられるので、その経験値を参考にしていただきたいと思っています。
この点ではブランド戦略経営研究所の会員でもあるメーカー、流通とかの比較的大きな企業や、調査企業、広告代理店などでは、ブランドやコミュニケーションということをよく考えておられるので、その経験値を参考にしていただきたいと思っています。韓国や中国、台湾などアジアの企業が急成長する中で、やはり日本、関西を元気にしなくちゃいけない。大阪ならやはり中小企業に元気になってもらわないといけないと考えているんです。
高崎氏: 仰る通りですね。
特に東南アジアとの関係になると、やはり価格競争がシビアになることもあって、どううまく対応していくかを考えなければいけないと思うんですね。
企業の例で言えば、PCですと、レノボグループという中国メーカーがIBMのPC部門を買収して、今やヒューレットパッカードを抜いてナンバーワンになった。でもノートPCですから、タブレット端末であるiPad等が出てきてる今、非常にシビアな競争になってくる。その中でブランドをどう立てていくかは、レノボとはいえ厳しいと思いますね。やや価格競争で勝っているところがあって、ブランドとしてはまだまだ弱いんじゃないかと思います。
高崎氏:私もヨーロッパやアメリカへは、このネジザウルスのビジネスを展開しているんですが、中国にはまだそれほど力を入れていないんです。 もちろん中国でもパテント出願していますから、何かあっても対抗できるんですが、やはりその前にまずブランド化が大事だろうと思っているんです。
仮にコピー品が出てきたとしても、いや、もともと本家はこっちだろうと、中国の人たちにもわかるようにしておきたいんです。その上で中国進出しようと考えています。それもブランドを意識した戦略ということになりますよね。
どんどんコピーが出てきたり、Appleのように先に中国にパテントを取られてしまっていた、ということのないように、知財で防御することはもちろんですが、如何にプロモーション等できちんと社会的に認知させ、ブランド・ロイヤルティを構築することが極めて重要ですから、そうしたブランドを意識した戦略は大事なことです。

高崎氏:ネジザウルスは現在、いわゆるホームセンターといった大手量販店等で販売されています。頭が取れてしまったネジを回せるというのは、「あってよかった」という商品ですから、よくご愛用者の方のブログで、「あってよかった。やっと出番があった」と書いていただいてるように、いわば火事が起きたときに使う消火器のようなもの。気軽に一家に1本備えていただけたらと思っていますので、できれば安く提供したいですけど、品質が良くなければいけないのでどうしても少し高めになりますね。

高崎氏:弊社のミッションと同様、品質が良く、あってよかったという安心と機能、それから遊び心のあるもの。いわゆる「モノマガジン」に載ってるような、本物志向の方が「持っておきたい」と思えるような、また、こだわりのものを贈りたいという方がギフトに使っていただけるような商品を出したいですね。


株式会社エンジニア 代表取締役
1955年神戸市生まれ。東京大学 舶用機械工学科卒業。1977年 三井造船(株)入社。ディーゼルエンジン技師として10年間勤務。1983年 米国レンスラー工科大学 修士課程卒業。1987年家業の双葉工具株式会社入社。2004年代表取締役社長就任。2013年創業65周年を迎える。主な受賞履歴:平成21年グッドデザイン賞ネジザウルスGT。DIY協会会長賞ネジザウルスGT。平成22年近畿地方発明表彰「大阪府知事賞」高崎充弘(ネジザウルス)。大阪ものづくり優良企業賞 ㈱エンジニア大阪ものづくり発明大賞高崎充弘(ネジザウルス)。平成23年iF product design award 2011受賞(Neji-SaurusGT)ドイツ・ハノーバー。大阪産業創造館サンソウカンアカデミー大賞 2部門受賞。発明大賞「発明功労賞」ネジザウルスGT。中小企業優秀新技術・新製品「優良賞」ネジザウルスGT。ホビー産業大賞受賞ネジザウルスGT。全国発明表彰「日本商工会議所会頭発明賞」受賞 ネジザウルスGT。知的財産管理技能士表彰(第一回)受賞 高崎充弘。平成24年文部科学大臣表彰「科学技術賞」(技術部門)高崎充弘。知財功労賞「特許庁長官賞」㈱エンジニア。
URL:http://www.engineer.jp
取材:2012年8月
| 2012/08/08 |