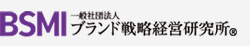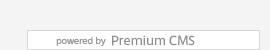HOME» ブランド対談 #06 »顧客満足度指数で見るブランディング
ブランド対談 #06
顧客満足度指数で見るブランディング

顧客満足度指数で見るブランディング
サービス産業生産性協議会課長 湯浅 勝浩氏
内閣府行政庁所管の公益財団法人 日本生産性本部内において、2007年経済産業省の協力により設立されたサービス産業生産性協議会。こちらでは主に日本を代表する大企業を対象に、JCSI(日本版顧客満足度指数)という調査・分析を行っておられます。このJCSIから見て、真の顧客満足とは何かについて語っていただきました。
 陶山: 通常顧客満足というと、事前の期待も高く利用後の納得感も高いことが望ましいということになりますが、このモデルでは期待と利益との関数で指数が出る。
陶山: 通常顧客満足というと、事前の期待も高く利用後の納得感も高いことが望ましいということになりますが、このモデルでは期待と利益との関数で指数が出る。つまり事前の期待が低ければ低いほど、利用後の満足が高いと満足度指数が高い。逆に事前の期待が高くても、利用後の満足度が低いと満足度指数は低いということになりますね。そこはこのモデルでいろんな企業を測定されてどうですか?
湯浅氏:この顧客満足度指数を経営に活かし、戦略レベルまで落として活用していただくには、単にお客様が満足しているかいないかだけではなく、顧客満足の要因と結果が必要になります。
もともと他のいろんな調査を研究してきたのですが、アメリカにこういう調査モデルがあるということで日本版にアレンジして開発されましたが、大きな枠組みは同じです。
お客様の満足を得るというのは、まず事前の期待を得ることは間違いないんですが、そうすると次の期待度は少しづつ上がってくるんですね。ある企業さんの場合、過去に顧客満足度が高い数値を出していたんですが、ここ最近新しい取り組みをしていないとなると、ロイヤルティが下がってくる場合もあります。
湯浅氏:やはり、少しづつ下がってきます。
ですが、お客様が事前に期待するというのは、その前に利用された経験に基づいて、「この企業のサービスはこういうものだ」という評価。その事前の期待を、「品質と価値」と「満足と価値」を分けて、トータルに顧客満足にどう影響するか。そこを問題意識として経営改善を目標とした経営指導やコンサルティングをされるという主旨なんですね。
湯浅氏: 仰るとおりです。
 陶山: そのJCSIの狙いは、具体的に企業さんにどう受け止められているかですが、宣伝やプロモーションの際に、「日本生産性本部のJCSIで顧客満足度1位を獲得しました。」と結果的に表記するだけになっているのか。
陶山: そのJCSIの狙いは、具体的に企業さんにどう受け止められているかですが、宣伝やプロモーションの際に、「日本生産性本部のJCSIで顧客満足度1位を獲得しました。」と結果的に表記するだけになっているのか。それよりも企業内部で、何が評価されて評価されなかったのかを分析する際に、このJCSIの手法が良かったという声があると、(JCSIの)大きな優位点になると思うのですが。
湯浅氏: そうですね。業界の位置づけやレベルが同じであっても、ビジネスモデルの特徴によって全然評価が違うこともあります。飲食業界ですと、ファミリーレストランやファストフード、専門店といった大分類がありまして、そこで見ると実は安い回転寿司やハンバーグ専門店などが高く評価されていて、ファミリーレストランは、相対的に低いんですね。実際日常感としてファミリーレストランには、あまり行かなくなりましたからね。
湯浅氏:今のお客様は、何を食べに行くかという目的が明確になっていて、ファミリーレストランは昔の百貨店の大食堂のような位置づけになってしまって、知覚価値は下がり気味なんですね。まあまあの期待はしてもその対価は回転寿司やファストフードを比較すると高くないですね。やっぱりお客さんはそう思ってるんだという確認ができるということでしょうか。
 陶山: 顧客満足に影響を及ぼす要因は3つあって、期待価値と知覚品質と知覚価値という、「期待」と「コストパフォーマンス」の関数ですが、顧客満足が高いのにロイヤルティは低いのかなぜか。リピートするロイヤリティに繋がっていくにはどうしたらいいのか。そこは企業が知りたいところだと思いますが。
陶山: 顧客満足に影響を及ぼす要因は3つあって、期待価値と知覚品質と知覚価値という、「期待」と「コストパフォーマンス」の関数ですが、顧客満足が高いのにロイヤルティは低いのかなぜか。リピートするロイヤリティに繋がっていくにはどうしたらいいのか。そこは企業が知りたいところだと思いますが。湯浅氏: このモデルのロイヤリティとは継続利用意向なんですね。たとえば鉄道でいうと、通勤電車で使っている電車だと、明日から違う電車を使うかといえば、使いたくても使えないということがあります。使うかもしれないという可能性ではなく、今後も続けて利用したいかという意向になります。
お客様に利用し続けていただくことと、利用されていない潜在的顧客をどうやって新規のお客様として利用していただくかという、トライアルとリピートが最終的な売上や利益という企業目標に繋がるので、そこが一番関心が高いのではないですか。
湯浅氏:顧客満足よりもクチコミやロイヤルティのほうが、実際の収益に繋がる指標としては重要かなと思われていまして、例えば1回利用して満足したけど、もう次は利用しないとなるともうそれっきり。企業としては新規のお客様を獲得することがもちろん大事なんですが、同じお客様に何度も利用いただいて、クチコミによって他人に推奨いただくことで新規のお客様を獲得することが重要ですから、実はこの部分が注目していただきたい指標かと思います。
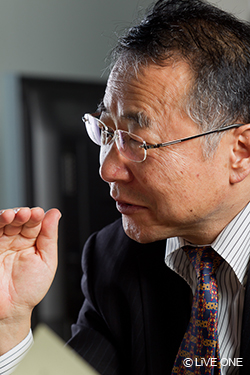 湯浅氏:日本の場合、苦情を言った経験があるかどうかを基点にしてしまうと、そもそもサンプル数が少なくなってしまうんです。あなたはその飛行機に苦情を言いましたか?とか、そのスーパーで苦情を言いましたか?というのは、日本人はほとんどそういう経験がありませんので、サンプルがなくなってしまうんですね。
湯浅氏:日本の場合、苦情を言った経験があるかどうかを基点にしてしまうと、そもそもサンプル数が少なくなってしまうんです。あなたはその飛行機に苦情を言いましたか?とか、そのスーパーで苦情を言いましたか?というのは、日本人はほとんどそういう経験がありませんので、サンプルがなくなってしまうんですね。
日本人の特性を考えて、苦情よりも、他人に良いように推奨するかしないかに替えていることが特徴です。
そういう意味では、消費者の態度の一つ、コンシューマーオピニオンの上位、先端的なところをを拾っているということはあるんですが、それの対極として「こだわりは強くないけど、良くないと思っている」、あるいは「こだわりは強く、すごく良いと思っているから、人に推奨する」といった、ポジティブな強弱と、ネガティブの強弱とのトータル4つを「クチコミ」という形で拾いたいという狙いがあったんでしょうね。
湯浅氏: ええ、日本人は自己主張が少ないので、その4つの項目の設定も、「これについて、あなたは好ましい話題としますか?好ましくない話題としますか?」と設問の段階で作りこんでいることも大きな特徴です。
ロイヤリティの仕様としてクチコミに焦点をあてる。情報発信源が企業ではなく、コンシューマージェネレーティブインフォメーションといった消費者基点のメディアが大きい。つまり今の消費者の購買動向を左右しているのは消費者自身だとというところが発想として出ていますね。
 湯浅氏: はい。「あなた自身が今後、それを使い続けるか」ということと、「周りの人に対して、あなたがどういう影響するか」というところですね。
湯浅氏: はい。「あなた自身が今後、それを使い続けるか」ということと、「周りの人に対して、あなたがどういう影響するか」というところですね。
湯浅氏: 具体的には、たとえばクチコミが50点、ロイヤリティが60点という場合、他にもサービス品質についてなどの設問を用意していますので、その理由がある程度わかるようになっています。
あと利用者の生の声もいただいてまして、その企業が何に評価されて評価されてないかということがわかります。調査も単純に100問聞くというだけでなく、ストーリーを形成して回答し易い、工夫された設計になっています。
コカコーラですとは6兆円のブランド価値がありますよという、ブランドが売買されるとしたら、どのくらいの金額で売買できるかというのは、その会社の値打ちをあらわす指標だと。ブランドやお客様の顧客満足は目に見えないけれど、なにか企業の経営指標として有用だというものだったり、こういう活動が価値にどう繋がるかということを知りたがってるところもこともある。
その中で企業にとってJSCIの顧客満足指数が、どんな価値があるのか、その点数が高いのが、業界の平均とか他社とくらべて相対的な地位としてのポジショニングがわかればいいですね。
湯浅氏:企業価値というということですね。JCSIの場合も、ドラックストアとコンビニエンスストア、百貨店といった、業界も規模も違う企業体も全く同じ横並びで比較することができるのも特徴なんです。
ただし、コンビニやドラッグストアの数字が伸びてきて、百貨店が落ちてきているという業界の傾向としてはあるんですが、企業ごとにその特徴が出てきていますね。
 陶山: 過去のトレンドもある程度わかってくるんですか?
陶山: 過去のトレンドもある程度わかってくるんですか?湯浅氏:そうですね。百貨店の売上が落ちてきているので、百貨店トップ企業のスコアが落ちてくるかというとそうではなくて、百貨店の利用者が半減しても、回答するのはその半減された中で聞いていますので。
湯浅氏: あります。特徴としてコアな人しか利用しない業界になると高くなります。
湯浅氏:ニーズとしてはあります。もともとJCSIを開発する段階で、デジタルカメラやパソコンも試行的にやった経緯はあります。
やはりモノに対する評価も入りがちだということもありますが、あくまでも私どもはサービスという形でこの調査をしていますので、デジタルカメラやパソコンがどれだけアフターサービスにニーズがあるかというと、今のところはまだ薄いということもあるので調査の対象から除いています。
今は製品のコモディティ化が進んでいますから大きな差が無いだろうと。今後、パソコンやTVに関してサービスで売っていくということになれば、調査の対象として復活する可能性もあるかもしれません。
湯浅氏:特に今後はそういう流れになってくるでしょうね。
そういう意味ではもう少し拡張したモデル化されて、いろんな業界対象に調査していかれると良いですね。サービスを提供するだけではない企業も多いですから。
湯浅氏: ニーズとしてはあるでしょうが、まだ消費者側もそこまで意識がないというか、 実際にデジタルカメラが故障したから修理して直すより、新しい商品を買い換えてしまうほうが多いこともありますね。
 陶山: 湯浅さんはこのJCSIから「ブランド」をどう見ておられますか?
陶山: 湯浅さんはこのJCSIから「ブランド」をどう見ておられますか?湯浅氏:AとBが互いにイコールになるという必要充分条件だと考えています。 企業側が伝えたいメッセージがお客様に伝えられていて、お客様もちゃんとそのメッセージを受け取っているということではないかなと思います。
会社のロゴマークを見るだけで、その会社がどういう会社なのか、その会社の提供しているサービスや製品がどんなもので、あるいは品質や信用・信頼・安心がどうあるかとかが解る。その一番の要因が顧客満足度ではないかと。お客様が満足しているとロイヤリティも高くなる。
湯浅氏:この調査自体はお客様の評価なので、この企業に対してこういうイメージを抱いている、それに対して企業がどのくらい応えているか、というのがこのJCSIに出てくる数値なんだと思います。
湯浅氏: イコールではないですね。
 陶山: イコールではないですか(笑) まあ、財務的な価値だとか売上利益といった企業の財務指標は一つの指標であるんですが、とりあえずそれはおいといて、ブランド価値というのは、消費者によって価値を評価されるものである、そういう性質をもっている。その消費者による価値評価の中で、最も重要な指標が顧客満足と言っても良いですね。
陶山: イコールではないですか(笑) まあ、財務的な価値だとか売上利益といった企業の財務指標は一つの指標であるんですが、とりあえずそれはおいといて、ブランド価値というのは、消費者によって価値を評価されるものである、そういう性質をもっている。その消費者による価値評価の中で、最も重要な指標が顧客満足と言っても良いですね。ブランドは製品や会社以上のものであると。たとえば製品やサービスに満足すると、そこからプラスアルファの付加価値がブランドによって提供される。
たとえばホテル業だと、その企業のサービスは特にリッチな気分になるといったような、実際にサービスを受けた機能的な便益以上の、何かエモーショナルなものが得られる。
つまりブランド価値というのはブランド固有の価値であるというのが一つの考え方にあるんです。
湯浅氏:顧客満足調査の中に、そのブランドを選んだことがあなたにとって、良い選択だったかということと、あなたの生活を豊かにすることにどれだけ役立ってますかという質問もあります。
機能的な利益だけでない概念的なものは入っていますので、ブランド価値と満足度は近いものがあるのでしょうね。実際に顧客満足が高い百貨店となると、何が買えるかということをを抜きにして、そこに行くことが良いということなんですね。
湯浅氏:この顧客満足度はいろんな質問を包含した結果ですので単に100点か0点かという話ではないのですが、ただそれを利用するだけで満足しているという要素も入ってます。
じゃあブランドによってリッチな気分をもたらすのは何かとなると、価値というところに落とし込んで、そこで企業側がどうマネジメントできるか、影響力を及ぼすことができるかというところ。
またそれをどうブランドコミュニケーションできているか、そのためにはどんなメディアメッセージをを使ってるかとかの、トータルで考えるのブランド戦略、ブランディングの考え方になる。その中に重要な要素としてJCSIがはいってると。
 湯浅氏: 完全にイコールではないんですけど、相関性は高いと思います。ブランド戦略自体はメーカーもサービスも関係なく、企業として取り組むべき課題だと。私ども協議会としては、調査だけでなく、サービス業全体の底上げということが目的でもありますので。
湯浅氏: 完全にイコールではないんですけど、相関性は高いと思います。ブランド戦略自体はメーカーもサービスも関係なく、企業として取り組むべき課題だと。私ども協議会としては、調査だけでなく、サービス業全体の底上げということが目的でもありますので。
努力しなくても儲かるというのではもちろんないんですが、うまく努力をして企業経営成果に結びつくしかけを考える。もっと効果的有効な事業のありかた、ビジネスモデルをご提案することは、大企業だけでなく中堅中小企業にも求められていますから。ボトムというか基本線を踏まえた上で、そこから高みを目指すというビジョンをどう考えていくか、方向性をプレゼンテーションするといった役目でしょうね。
湯浅氏:これで絶対成功するというのであれば皆さん飛びつくでしょうが、そうではなく「落としてはいけない部分」という意味だけでも理解していただければと思います。
公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会 課長
1973年生まれ。1996年~2000年 交通計画専門のコンサルティング会社に勤務。2001年に社会経済生産性本部(現 日本生産性本部)に入職。2011年までの10年間はコンサルティング部に所属し、中堅中小企業を対象とした経営コンサルティング、研修プロデュース業務に従事。2011年4月より現職。JCSIの開発・改善・実施・広報・企業支援などの業務を主に担当している
公益財団法人日本生産性本部
URL:http://www.jpc-net.jp/
サービス産業生産性協議会
URL:http://www.service-js.jp/
※JCSI(日本版顧客満足度指数)は約20年前にアメリカで開発されたACSI(The American Customer Satisfaction Index )を参考に独自に開発された調査モデル。統計的な収集方法による総計10万人以上の利用者からの回答をもとに、日本の幅広い産業をカバーした日本最大級の顧客満足度調査として、年間32業種・業態、約400企業・ブランド(2011年実績)の調査が実施されています。
※JCSIモデル構造は以下の6つの項目を指数化した数値で構成されています。
「顧客満足」利用して感じた満足の度合い
「顧客期待」利用者が事前に持っている印象や期待・予想
「知覚品質」実際にサービスを利用した際に感じる品質への評価
「知覚価値」利用者が感じる納得感・コストパフォーマンス
「クチコミ」利用したサービスを肯定的に人に伝えるかどうか
「ロイヤルティ」今後もそのサービスを利用し続けたいかの利用意向
取材:2012年11月
| 2012/11/17 |