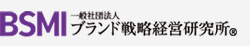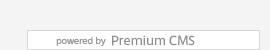HOME» ブランド対談 #10 »「食文化をクリエイトする」老舗外食ブランドのイノベーション
ブランド対談 #10
「食文化をクリエイトする」老舗外食ブランドのイノベーション

「食文化をクリエイトする」老舗外食ブランドのイノベーション
文野氏は、創業40年の老舗「大阪王将」を事業承継された後、その経営手腕を発揮し、全国のみならず海外6カ国にも進出、2012年には400店舗を達成されました。チェーン店としていち早くセントラルキッチンを導入され、「よってこや」や「太陽のトマト麺」など、数々の業態を展開される傍ら、食品メーカーとして冷凍餃子「大阪王将」を販売されています。
外食と中食の双方を両輪を展開される同社社長に、外食産業として、食品メーカーとして、今後求められるものは何か、さらに老舗としてブランドを守る戦略を語っていただきました。
 陶山: 今、流通サプライチェーンのPB(プライベートブランド商品)が全盛で、メーカーや外食産業は、今後の展開をどう図るかの岐路にさしかかっているようですね。
陶山: 今、流通サプライチェーンのPB(プライベートブランド商品)が全盛で、メーカーや外食産業は、今後の展開をどう図るかの岐路にさしかかっているようですね。文野氏: それはすごく感じます。もっと怖いのが、ライフスタイルが中食化しているという大きな流れがあって、外食産業は非常に厳しくなってきています。
そこで外食チェーンとして培った信用力や商品開発力を、中食にどう持っていくかですが、メインである餃子の冷凍食品で大手に対抗しておられますね。
文野氏: でも今の段階では超えられていませんので、まさしく今、2位が1位を抜くための「ダントツアイデア」というプロジェクトを始めています。
それには徹底した違うポジショニングだと考えていて、例えばアフリカのサバンナには、ライオンがいてシマウマやキリンもいる。強いものだけが勝つのであれば、ライオンだけになってしまいますが、ちゃんと棲み分けられるはずなんです。
その棲み分けるためのポジショニングを、外食をうまく活用しながら見際めていくことが非常に需要だと考えています。冷凍食品には「冷凍だから」という妥協感が、常識として何かに括られているものがあって、そこを打ち破っていくしかない。具体的には本質化という方向性ですね。
文野氏: それはもう食感しかないと思うんです。
 文野氏: 冷凍食品の食感というのは、低い次元で常識化しているんですね。その食感を破れば、突き抜けることは可能になると思うんです。でもそれには新技術が必要になりますから、大学等と提携するなりで開発していこうという方向性です。
文野氏: 冷凍食品の食感というのは、低い次元で常識化しているんですね。その食感を破れば、突き抜けることは可能になると思うんです。でもそれには新技術が必要になりますから、大学等と提携するなりで開発していこうという方向性です。
文野氏: 袋麺は基本的には縮れているものなんですが、それを無くしたというのは新しい。でもそれが昔からなかったかというと、あった技術なんですね。それを袋麺に活用したという着眼は素晴らしいですし、非常に評価に値することだと思います。
また、嬉しいと思うのは、そういうところに消費者が反応し出してきているということ。つまりインスタントや冷凍食品に反応するということは、明らかにそのジャンルを「料理」として見てきているということなんですね。だからチャンスがあるなと。
文野氏: 新技術や発想の転換で、業界の常識を打ち破りたいと考えています。スーパーの冷凍食品売り場を見ていただくとお分かりなんですが、良く似た規格のパックなんです。もちろん商品もロゴも違いますが、パッと見て全部同じ商品に見えるほど見栄えがないんですよ。
そこでじゃあ三角形のパッケージをつくろうとなっても、棚効率が悪いからダメという話になる。確かに三角形のパックだと、棚に並べたらロスが出る。そこが致命的なんですね。そういった業界の常識を変革したいのです。
冷凍だからストックができて便利、という発想じゃなく、「冷凍だからこそ美味しい、冷凍だからこそフレッシュ」といった価値提案に取り組んでいます。
 常識外の規格でも置いてもらえるものに繋げられないかと。そういう商品をなんとか提案できるようにしたい、とプロジェクトを始めています。
常識外の規格でも置いてもらえるものに繋げられないかと。そういう商品をなんとか提案できるようにしたい、とプロジェクトを始めています。
割引セールの時に買いだめをするストック需要や利便性だけではない新たな価値を創造し、冷凍食品業界の常識を変革できるかが、今後の成長の鍵を握っています。そこをどう乗り越えるのか、或いはどの会社が乗り越えるかなんです。
そういうグラウンドを変えることが、D・A・アーカーの「戦わずして勝つ」。つまり全く別のカテゴリーとしてポジショニングし、ニューバリューを提供するということですね。
文野氏: 仰る通りです。冷凍・常温など分野はさまざまありますが、今の規格は全部一緒なんですね。そこにバイヤーを超える、或いはバイヤーの支持を得られる価値のものができれば、確かに世界は変わりますね。
文野氏: ええ、そこは痛切に感じています。規格と値段で決められますから、ひと目でわかるような説得力のある商品を持っていかないと始まらない。そこは外食ブランドと冷食の、両方のシナジーで持っていけることが強みですし、その説得力があるのは事実なんです。
 陶山: 以前に高齢者にどういう冷凍食品を提供するか、またその価値は何かという調査をしたことがありますが、やはり冷凍食品に対してネガティブなイメージを持っていますね。
陶山: 以前に高齢者にどういう冷凍食品を提供するか、またその価値は何かという調査をしたことがありますが、やはり冷凍食品に対してネガティブなイメージを持っていますね。その一つに「冷凍のほうれんそうにはシャキシャキ感がない」と仰るんですね。でも今の冷凍のほうれんそうってほんとに美味しい。
文野氏: びっくりしますよね。
文野氏: だからこそ外食は、小さくてもエンターテイメント性を求められると思います。
文野氏: 外食はどういう価値を見出すべきなのか、というところですね。オーナーシェフや個店の場合は、ある意味(価値が)あるのでしょうが、チェーンとしての役割りですね。本来、外食に求められるのは、間違いなくエンターテイメント性ですから。どんな日常食を売っていても、新しい非日常というものを求められる。そこに何を提供できるかを、根本から考え直していかないといけないのでしょうね。
文野氏: それもひとつの生き方でしょうね。
 文野氏: 今、セルフうどんが年間100店舗以上のスピードで伸び続けていますが、それが外食の実態なんです。そういうことで外食は反応していくんだというレベルなんですね。
文野氏: 今、セルフうどんが年間100店舗以上のスピードで伸び続けていますが、それが外食の実態なんです。そういうことで外食は反応していくんだというレベルなんですね。
つまり求められているものが非常に落ちている。あのオレシリーズも原価率75%で非常に価値のある商売なんですが、いわゆる「立ち食い」なんですね。
マクドナルドや我々の「大阪王将」が流行っていることも含めてですが、今の外食に対して求められている何かというのは、語弊もあるでしょうが、非常に程度の低いものなんです。はたしてこれで良いのかなと思うんですね。
基本的にセルフはセルフなんですけど、なにか突き抜けるものがポンと一つでもあれば、そこがウリになってお客様に評価されると。
文野氏: なによりもお安いですしね。だから受けているし、トレンドに合っているんだろうなとは思うんですけども、やはり冷静に考えれば「セルフ」なんですね。ですから昼には行くけど、やはり夜にはあまり行かれない。
外食というのは夜流行るということでないと。その空間で1時間半や2時間過ごせる業態が流行ることが、本来の豊かさの象徴だと思うんです。外食産業全体がもっとイノベーションを興していかないと、ますます中食化という大きなライフスタイルの流れを、逸すことができないんじゃないかと思いますね。
 文野氏: 今「大阪王将」も含めて、マクドナルドもしかり、セルフうどんしかり、勝ち組と言われているのは皆、40年前からある業態なんです。ということは今だにそれしかない。ディテールでいえば店舗のデザインにしてもメニューにしても、さまざまにマイナーチェンジしながら小さな変換をしてきていますが。
文野氏: 今「大阪王将」も含めて、マクドナルドもしかり、セルフうどんしかり、勝ち組と言われているのは皆、40年前からある業態なんです。ということは今だにそれしかない。ディテールでいえば店舗のデザインにしてもメニューにしても、さまざまにマイナーチェンジしながら小さな変換をしてきていますが。
だけど本当にやらなければいけないのは、もっと新しいところ、たとえば朝やアイドルタイムのような時間帯などに、今までなかった便利さやスタイルを提供するといったことなんですね。それが本来の「食文化を通じて生活文化に貢献する」ということだと思うんです。
文野氏: 朝の時間帯をしっかり獲った外食といえばコメダコーヒーですが、そのコメダコーヒーもやはり40年前からあるんです。だからスタイルとするとあまり変わっていない。名古屋ローカルを全国展開してるだけなんですね。朝の食事はその日のモチベーションを左右すると言いますから、そのきっかけになるような食文化。本来そういうところに対して半歩先の提案をすることが使命なんでしょうね。
文野氏: 大事なのは外食だけで括らないことだと思います。外食も中食も、同じ目線でフラットに物事を考えられる企業体質にすることが一番重要だと。今そこに向けて出発し始めていますので、今後は大きく変わってくるだろうと思います。
 陶山: ある高級アイスクリームのメーカーさんにも、ライバルは同業他社ではなく、コンビニのスィーツだと伺ったことがあります。外食であるけれど、中食の枠を越えなくてはいけない。いわゆるボーダレスというところなんでしょうね。
陶山: ある高級アイスクリームのメーカーさんにも、ライバルは同業他社ではなく、コンビニのスィーツだと伺ったことがあります。外食であるけれど、中食の枠を越えなくてはいけない。いわゆるボーダレスというところなんでしょうね。ボーダレスというと、今海外でも展開されてますが、たとえば中国ですと中華料理は本場ですが。
文野氏: 中華で勝負していないですね。ジャパンチャイニーズといって、6割のチャイニーズと4割の日本食をフュージョンさせた業態で進めています。
文野氏: イタリア料理もフランス料理もそうですね。本場と違い日本化していますから。そういうことなんでしょうね。
文野氏: シンガポールではそれがうまくいきました。我々がプロデュースするよりも、長年現地に住む日本人のスタッフが、いろいろ決めて進めていきましたから。非常に的を得たメニュー構成になっていて、売上も上がっています。
文野氏: まずは100を一つの基準にしていますが、500店舗くらいは考えています。でも今はまだ、どの国に重きをおいて出店しようか決めているところですね。ひと先ず6カ国に出店しましたが、それぞれの反応を見ながら、一番感触のあるところに集中しようと考えています。
 陶山: ロジスティックス含めコスト的にも、ペイできるエリアを決めて集中する、ドミナント出店でないと意味が無いですからね。今はテストマーケティングの段階なんですね。
陶山: ロジスティックス含めコスト的にも、ペイできるエリアを決めて集中する、ドミナント出店でないと意味が無いですからね。今はテストマーケティングの段階なんですね。文野氏: ええ。でも明らかにお客さんが若いことに、日本との違いを如実に感じますね。10~15歳は違います。
文野氏: まだ30歳前ですか。それは若い。
逆に日本は高齢化が進んでますが、高齢者向けといっても「お年寄り向け」というとダメなんですよ。「自分はまだ若い」と当該のお客様から敬遠される(笑)
年齢ではなくマインドの問題ですから、そういうターゲティングされることに対して抵抗感があるんです。私もそういう域に達しつつありますけど、いつまでも学生と一緒に若者ぶってますが(笑)
文野氏: 老けようがないですよね、先生は(笑)
文野氏: やはり買いたい物、食べたいものを消費していくことが一番ですね。そのきっかけとして、マラソンや音楽、ダイビングなどのコミュニティに意識的に入って、若い人達と一緒に消費することでしょうか。やはり好奇心ですね。この好奇心があるうちはまだ大丈夫かなと(笑)
 文野氏: 元々というより「新しい価値を創造する」という、そもそものミッションが会社にあって社長をやっていますので、なんとかそれを実現したい。
文野氏: 元々というより「新しい価値を創造する」という、そもそものミッションが会社にあって社長をやっていますので、なんとかそれを実現したい。
それがどんどん時間が迫ってくるという気持ちの中で、もう1ミリの情報も無駄にしたくない、見過ごしたくないと、やたら視察に行ったりしていますね。
文野氏: 今こうした成熟社会ですから、フルフルのおなか満タンというよりも、自分の価値に見合った満足が「おなかいっぱいの幸せ」に置き換わってきていると思っています。 今小さいのに高い高級チョコレートや、1粒1000円のイチゴがあったりしますね。1000円というのはそんなに高い金額ではないけれど、1粒となると高い。でも飛ぶように売れていると。
そういう自分の満足が幸せというところに、日本の場合は価値観が変わってきています。そこに対して新しい価値を提供できるよう、さらにクリエイティブな集団にもっていかないといけないと非常に感じています。
そこが「アンド」であるという。お客様ご自身が、これまでのバックグランドや将来の展望の中で、「あ、これがアンドなんだ」ということを見つけ出すことが喜びになるんじゃないかと思いますね。
文野氏: 本当に仰る通りです。そうなんだそうなんだって、整理していただいたような(笑)

文野氏: 我々は「料理人」ですので、どちらがということはないですね。料理人であるからこそ、価値が出ると考えています。外食と中食の両方から新しいお客様を発掘していく、というシナジーが一番大切です。どちらがへこんでもダメですし、両輪を走らせていくというのが基本的になりますね。
文野氏: それは進化ですね。マクドナルドがその典型で、完全に違う店になっています。セルフうどんもそうです。セルフという業態は昔からありましたが、今の時代に合わせた空間作りや、本物感、しずる感を出すという進化をされています。やはり進化しなければ残れないですから。
文野氏: 餃子をメイン商品として40年、我々としては、餃子は匂いがして当たり前、匂いがあるから美味しいんだ、という思い込みがあったんです。それはその通りなんだけども、一方で匂いが消えて欲しいという人もいた。そこで匂いはそのままにして、体内に入ってから匂いを消す、という着眼点にふと変えたとき、そういう餃子を便利に感じる人達が食べ出した。それで売上が伸びた。そういうことなんですね。思い込みって怖いなと思います。メインの商品を変えるのは、非常に勇気がいりましたけど。
つまり絶え間ない進化の中には、成功もありますがそれ以上に失敗もある。常に山あり谷ありで諦めず、変えていかないといけないという気持ちと、重要なのは時代の空気読むこと。アンテナの感度はどうしても鈍ってきますから、常に感性を磨ぎ澄ませていないといけない。それにはやはり外の空気に触れて、自信と誇りを持ちながら、そこに安住せず一歩踏み出すということですね。
1959年大阪府生まれ。1980年 大阪王将食品株式会社入社。1985年 同社後継社長に就任。1993年 平成5年9月冷凍食品販売を開始。1996年 株式会社大阪王将に社名変更。1997年 「よってこや」ラーメン事業展開開始。2002年 イートアンド株式会社に社名変更。2003年 「大阪王将」関東に進出。2004年 海外進出「大阪王将」香港1号店。2006年 新業態「太陽のトマト麺」展開開始。2011年 大阪証券取引所ジャスダック上場。2011年大阪王将300店舗達成。2012年 東京証券取引所市場第二部上場
イートアンド株式会社
http://www.eat-and.jp/
取材:2013年3月
| 2013/03/20 |