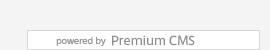HOME» ブランド対談 #14 »[ブランド対談]カカオを通して世界を変える
ブランド対談 #14
[ブランド対談]カカオを通して世界を変える
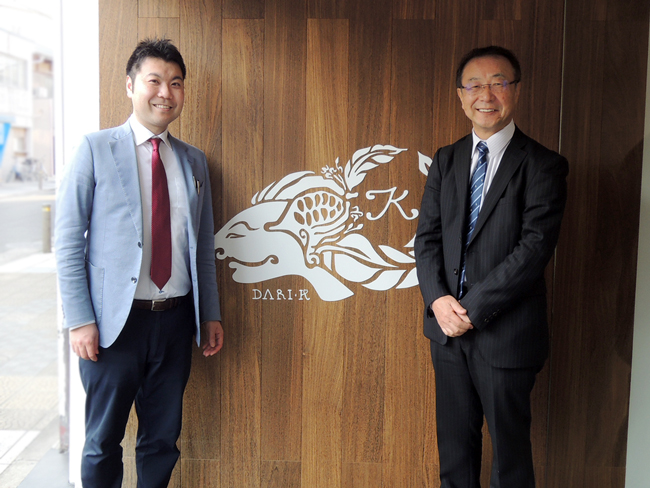
カカオを通して世界を変える
品質の良いカカオ豆を安心・安全に消費者へ届けるため、インドネシア・スラウェシ島の契約農園から直接買い取り、カカオ豆の焙煎からチョコレート製造までを一貫して行う本格的な「Bean to bar」のパイオニアとして注目されました。
その良質なカカオを自家焙煎して作り出される新鮮なチョコレートは、毎年パリで開催されている世界最大のチョコレートの祭典「サロン・デュ・ショコラ」にも出展、C.C.C.品評会でも銅賞を受賞するなど、国際的な品評会でも評価を得ています。
また、2016年にはインドネシア現地法人、PT.Kakao Indonesia Cemerlang(KIC)を設立され、生産地をより豊かにするため、カカオを通した国際協力のプロジェクト活動を展開されています。
今回のブランド対談は、一般社団法人ブランド戦略経営研究所理事長、関西大学 陶山計介教授が同社を訪問、Dari K 株式会社(文中での呼称は”ダリケー”)の設立の経緯やビジョン、そしてチョコレートの美味しさとともにそのソーシャルなミッションをお客様にどのように伝えていくのか、お話を伺いました。
吉野氏: たまたま旅行で訪れた韓国のカフェで、世界のカカオ豆の産地が載っている世界地図を見たんです。それまで自分の中では、カカオ豆といえばガーナと思い込んでいましたが、そうではなくて一番多いのがコートジボワール。次がガーナ、そしてインドネシアが三位でした。そこで、なぜアジアのインドネシアからカカオ豆を買わないのだろうと疑問が浮かびまして、現地に行ってみたのがきっかけです。
実際に現地に行くと、確かにカカオは栽培されていましたが、そこで見た光景というのは、農家の皆さんはあまり生き生きとしていないんですね。こんなにたくさんカカオが採れるのに、なぜみんな生き生きしていないのだろうと思って話を聞いてみると、実はカカオの価格は国際相場で決まっていて、どんなに一生懸命良いカカオを作っても、その努力が報われないんだと。それを聞いて、そんな世の中はおかしいのじゃないかと思ったんです。
じゃあ、自分に何ができるだろうかと考えたとき、良い品質のものは高く買うという当たり前の大原則を持ち込めば、それは農家にとって所得も上がるし、自分たちにとっても良いカカオが手に入ることになり、ビジネスと社会貢献が同時に成り立つと考えたんです。
吉野氏: そうですね。もともとチョコレートが好きだったというのはありますね。なので、これがもしコーヒー豆で同じことに出会っていたとしたら、やっていなかった可能性は高いです。

吉野氏: ダリケーを始める前はやはり、チョコレートは日常的なお菓子、それも、「商品」としてチョコレートを見ていましたが、今その「商品」を販売しているかというとそうではなくて、素材から作り、自分たちの手を加えることで、どんな品質にも変えられる可能性があるもの。努力と工夫次第でどんなふうにも化けさせることができる魅力的な素材といったところでしょうか。
吉野氏: はい、そうですね。今コンビニやスーパーで売っている「商品」としてのチョコレートというのは、これは大きなくくりでいくと、コモディティ商品だと思います。その中でダリケーは何をしようとしているかというと、チョコレートの脱コモディティ化。そこにはいろんな可能性があるわけです。
コモディティとして大量生産、大量消費で価格が相場で決まるという、この原則をふまえながら、自分たちがサプライチェーンの川上から川下まで携わることで、いかに個性をもった、その時々のスペシャルなものとして出せるか、というところがチャレンジでもあり、おもしろ味でもあると考えています。

吉野氏: (ものづくりを)やってみたいという気持ちはありましたね。というのも投資の仕事というのは、結局は出来上がったものに対するコメンテーターなんです。料理に例えるならば、出来上がった料理に対して評価をする、分析をする。これはこういうところが美味しいから何点。点数が高ければ投資する、というのがそれまでの仕事でした。
でもこのチョコレート作りというのは、原料から商品を出荷するまで自分たちで行う。しかも商品の良し悪しを判断するのは消費者側ですが、自分たちがその価値をいかようにもできるという、ものづくりのダイナミックなところはすごく憧れでもありました。逆に、自分はこれまで最終商品のジャッジしかしてこなかったので、その前の工程でどれだけできるかというのは、半分自信もありましたが、半分不安もありました。
ただ川上のカカオ豆から川下のチョコレートまでにいたるストーリーと世界観、そこにいわゆるソーシャルな要素を見出す点にダリケーのユニークさがあります。2011年に会社を設立される際、こういうビジョンやミッションは、マーケティングのセオリー、とくに自社の強みや弱みについてのSWOT分析をした上で決められたのか、あるいは吉野さんご自身の義憤や使命感みたいなものがあったのですか?
 吉野氏: 正直言うと、初めはあまり考えていなかったですね。自分がチョコレートをやろうとしたときに、業界内のどこを狙ってとか、他社と比較してどういう立ち位置で競争すべきとか、そもそも業界の様子も分からなかったので、その戦略的なマーケティングのポジショニングというところはあまり考えていませんでした。もうその時の衝動で、「ああ、これはなんとかしないといけない。なんとか自分たちで良いカカオを日本に持ってきて売らないと現状が変わらない」という気持ちで始めたところが大きかったですね。
吉野氏: 正直言うと、初めはあまり考えていなかったですね。自分がチョコレートをやろうとしたときに、業界内のどこを狙ってとか、他社と比較してどういう立ち位置で競争すべきとか、そもそも業界の様子も分からなかったので、その戦略的なマーケティングのポジショニングというところはあまり考えていませんでした。もうその時の衝動で、「ああ、これはなんとかしないといけない。なんとか自分たちで良いカカオを日本に持ってきて売らないと現状が変わらない」という気持ちで始めたところが大きかったですね。
ただそれで万々歳で売れていくかというと、やっぱりそうではない。他社はどういうものを出しているだろうか、大手メーカーとの違いをどう出していこうかと、だんだん経営のほうに目を向けるようになってくる。そこで何をもって差別化するかを考えていくと、コストは大手メーカーと比べると優位にはならないし、商品の見た目や派手さといった技巧的な部分にプラスがあるかというと、やっぱり何十年もキャリアのあるショコラティエやパティシエには勝てない。となったとき、自分たちしか出せないところは何かというと、それは現地の農家さんとの協働だと。
吉野氏: まずエスコヤマの小山さんやパレドオールの三枝さんといった、今成功している人たちの共通項は何かというと、自身がパティシエであり、ショコラティエとして技術がある。さらにどこかで修行をされてきたキャリアもある。じゃあ自分はというと、その成功している要因は何も持っていませんから、ここは頭でロジカルに考えてしまうとアウトだったと思います。でもハートで動くことで、素人ながらも最初の一歩を踏み出したところが良かったのかもしれないですね。

吉野氏: そうですね。2011年にダリケーを始めた頃、「bean to bar」という言葉は、海外では出てきていましたが、日本では誰もやっていない、参考にするところも無ければ、ベンチマークもできないといった状況でした。
2014~2015年くらいから、コーヒーでいうと「サードウェーブ」、チョコレートの「bean to bar」、いわゆるクラフト、手作りというのが、世界でも日本でもトレンドになってきたこともあって、日本の「bean to bar」のパイオニアとして注目されました。ただ今になってみると、「bean to bar」の市場は大きくなってきたことは良いものの、プレイヤーの数もこの2~3年で100社以上に増えました。
 吉野氏: そこは厳しいのですが、「bean to bar」のパイオニアとして、先行した優位性を持続できているかというと微妙なところです。おそらくその一番大きな要因は、そもそも「bean to bar」というのは、カカオ豆は国によってこんなに違いますよ、というのが醍醐味であって、ダリケー以外のメーカーは例外なくいろんな国のカカオ豆を使っているわけなんですね。
吉野氏: そこは厳しいのですが、「bean to bar」のパイオニアとして、先行した優位性を持続できているかというと微妙なところです。おそらくその一番大きな要因は、そもそも「bean to bar」というのは、カカオ豆は国によってこんなに違いますよ、というのが醍醐味であって、ダリケー以外のメーカーは例外なくいろんな国のカカオ豆を使っているわけなんですね。
にもかかわらず、ダリケーの「bean to bar」は、ずっとインドネシアのカカオ豆、むしろ素材としてあまり良くなかったものを良くするということにこだわっている。つまり、人々が捉えている「bean to bar」と、自分たちがやっている「bean to bar」というのは、製法は同じだけどコンセプトは違っているということなんです。
なので、最初はやっぱり他に無いので取材がくる、テレビにも取り上げられるというのも多くありましたが、だんだん、いろんな国のカカオ豆を使う他の「bean to bar」メーカーがポンポン出てくるのに従って、目新しさも伴ってそっちに持っていかれたというところですね。
吉野氏: ここが板挟みのところなんですが、お客様のニーズやウォンツはこういうところにある。それを認識できているなら、それに合わせていくのが通常の企業としての対応です。でもそこで、「bean to bar」メーカーとして成功したいのではあればそれでいいですが、そこをやりたくて自分は起業したのか、そのために今の社員が集まってきたかというと、そうでは無いんです。
やはり現地の農家とカカオ豆の買い取りの慣習を、いかにきちんと品質をベースにして変えられるかどうかが重要なので、そもそもそこを変えられなければ、この企業の存在意義が無いと考えているんです。とはいえ企業を存続させていくためには、消費者ニーズも汲まなければ商売にならない。じゃあ両方やればいいかというと、今の人員や経営資源を考えると両方は難しい。言い訳になってしまいますが、そこは苦戦しているところです。

それと同様にチョコレートを食べるときも、普段食べている大手メーカーのチョコレートじゃなくて、今日はダリケーのプレミアムチョコレートにしようというときは、そこに何か特別感があるんじゃないかと思うんです。じゃあその特別感はどういうものなのか、お客様はそれに何を期待しているのか。そのあたりのお客様のニーズをどう考えておられますか?どんなお客様にダリケーのチョコレートは支持されているのでしょうか。
吉野氏: そうですね。まず大手メーカーはどういうニーズを満たすための手段としてチョコレートを提供しているかというと、一般のお客様が美味しいと思うおやつ、というところですね。また、「bean to bar」に関していうと、産地によって味が違う、そのこだわりを楽しむため。ダリケーはというと、チョコレートを売っているのは同じだけれど、最終的な目的が2つあるんです。
1つは生産者と繋がれること。そんなチョコレートって他に無いんですね。他の「bean to bar」のチョコレートやコンビニやスーパーで売っているチョコレートは、生産者がどんなふうにカカオを育てて、どういうふうに加工しているのかなんて全然わからない。でもダリケーのチョコレートは、ホームページやリーフレットを見れば、こういう形で作られているんだという一貫性が見えるので、ここは特別な目的だと考えています。
もう1つはソーシャルな意義とは別に、他のチョコレートは工業的なマスプロダクションになっている以上、油を入れたり香料を入れたりしていますが、ダリケーのチョコレートはカカオをつぶして砂糖を入れているだけ。シンプルに混じりっけのない本当のカカオを食べられるというところなんです。

成功への道筋というのはいろいろありますが、明治の「ザ・チョコレート」も一つの成功例ですし、小山さんや三枝さんといったパティシエやショコラティエの方たちのやり方もある。でもそうではない、第三、第四の方向性やパスがあると思うんですね。それがまさにブランドになっていく。
 ブランド論の第一人者デービッド・アーカー博士は、企業のブランドとは製品や企業以上を超えるもの、メンタルやサイコロジカルな形の無い要素が重要だと言っているんですね。そうした要素を提供できるということは、まさにブランド力がつくということだと。じゃあそのブランド力とは何かというと、実際には商品であったりマーケティングによって構築されますが。
ブランド論の第一人者デービッド・アーカー博士は、企業のブランドとは製品や企業以上を超えるもの、メンタルやサイコロジカルな形の無い要素が重要だと言っているんですね。そうした要素を提供できるということは、まさにブランド力がつくということだと。じゃあそのブランド力とは何かというと、実際には商品であったりマーケティングによって構築されますが。BSIは地域ブランドにも携わっていますが、最近の例でいうと熊本にある肥後製油の「プラスオイル」。これはなたね油にトマト、にんじん、ほうれん草といった野菜の抗酸化物質を浸透させた食用油なんです。2年前(2016年)に起きた熊本地震の復興に向けた取り組みとして、地元熊本の農家さんの野菜を使っているんです。
こうした動きは古くは雪印乳業(現雪印メグミルク)も「健土健民」という思想、大地が健やかであると健やかな牛が育ち、美味しい牛乳ができる。すると民も健やかになるという考え方を持っておられます。そうした大地の力や恩恵をどう活用するかというところがブランドのストーリーになっていく、というところですね。そこには素材や製法のこだわりだけでなく、デザインやパッケージ、またプライシングなんかも大事な要素になりますが。
吉野氏: 消費者にとって、ダリケーと他社のチョコレートと何が違うの?となったとき、微妙な味の差はなかなか分かっていただけないと思うんですね。他社と比べて負けはしないけど、それが大きく差別化要因になっているかというと、「全然違う」とはならない。まして価格の面となるとやはりダリケーは高いわけです。
じゃあ何がダリケーの特徴かというと、大量生産する大手メーカーができないような現地の情報、カカオがどうやって栽培されているのか、いつ作っているのかというトレーサビリティが明確なところです。でも、商品をパッと見てその提供価値が分かるかというと見えていない。見えないなら価値として機能していないじゃないかとなってしまっているんでしょうね。
 今先生が仰ったように、大地を良くすれば植物が良くなり、それを食べる人間も健康になるという、そういう説明なら、自分たちが食べるものって美味しいだけじゃなくて健康に良いものが良いよね、となりますね。だったらチョコレートであれば、その素材はカカオ豆だから、植物として良いカカオを食べたいよね、でもその良いカカオが採れるには、良い土壌で栽培されていないといけないよねと。そういう表現でいくとすごく分かりやすいと思いました。一般の消費者にとって、インドネシアの誰々さんが作ったカカオ豆、というだけじゃないんだと。これは大きなヒントになりました。
今先生が仰ったように、大地を良くすれば植物が良くなり、それを食べる人間も健康になるという、そういう説明なら、自分たちが食べるものって美味しいだけじゃなくて健康に良いものが良いよね、となりますね。だったらチョコレートであれば、その素材はカカオ豆だから、植物として良いカカオを食べたいよね、でもその良いカカオが採れるには、良い土壌で栽培されていないといけないよねと。そういう表現でいくとすごく分かりやすいと思いました。一般の消費者にとって、インドネシアの誰々さんが作ったカカオ豆、というだけじゃないんだと。これは大きなヒントになりました。
例えば、日本コカ・コーラの「い・ろ・は・す」や、サントリーの「天然水」には、ペットボトルにちゃんとこだわりが詰め込まれていますね。リサイクルを促すためにペシャっとつぶれるようになっていますとか、取水地の緑を守っていますとか、そうしたソーシャルなメッセージがパッケージを見ると分かりますし、プロモーションや広告にも表現されています。
限られた予算や資源の中で何にプライオリティを付けながらそれをどう伝えていくか。他の競合他社と違うところをどうアピ―ルしていくか。そこがブランドポショニングになりますから、SWOT分析でどこを狙うかというターゲティングはしておかないといけないのかもしれませんね。

吉野氏: 全社的に見ると伸びてきています。ただ直営店に限って見ると若干下がっているんですね。じゃあどこが伸びているかというと、1つはEコマース(オンライン通販)、もう1つは卸です。割合としては、直営店が4割、Eコマースが1割、あとの5割が卸になっています。
吉野氏: そうです。今年(2018年)3月に京都駅前地下街のポルタがリニューアルして、そこでダリケーのチョコレートも買っていただけるのですが、京都らしさを出そうと抹茶味の商品を出したんですね。でも抹茶味のチョコレートというのは、 “京都らしさ”はあるけれど、抹茶を土台にするとカカオの香りが消えてしまう。それってダリケーのカカオを使う意味があるのかと、社内でもかなり意見が出ました。
でもその“京都らしさ”を求めているお客様がいる以上、チョコレートが好きな人に喜んでもらいたい。そこを逃しても100%いけるのであれば良いですが、今はまだそうじゃないと考えたんです。京都らしさもあって、子どもやお年寄りにも美味しく食べていただける味。それならこれはこれで市場が取れるんじゃないかと作ってみたんです。すると案の定、皆さんに好まれています。

吉野氏: 抹茶チョコレートって想像以上に受けがいいんだなとあらためて驚きました。でもこれはメインのトリュフ(チョコレート)と比較すると、かなりコマーシャライズした商品です。ダリケーのトリュフが好きな人がこれを買うかというと、買わないかもしれない。「これはダリケーの商品じゃない、ダリケーってやっぱりトリュフじゃん」と。
結局分かったことは、自分たちが本当にやりたいことは何か、自分たちの強みは何かというと、やっぱり川上のところに戻っていくので、そちらに注力していこうとなったんです。これも必然だったのかもしれませんね。店頭売りの売り上げが少し落ちてきたということは、それに気づくタイミングだったのかなと思います。
吉野氏: そうですね。通常大手メーカーがチョコレートを作るとき、そのカカオの実が木になっていたのはいつなのかというと、大体2~3年前です。そもそも正確にわかるすべがない。でもダリケーは現地に会社をおこして、農家から直接買っているので、採れたてを日本に送ることが可能なんですね。すると今日作ったチョコレートのカカオ豆は、いつ木になっていたかというところまで全部把握できているので、そのフレッシュさを売りにできる。
ボジョレーヌーボーも、ボジョレーのワインが解禁日に一番美味しいかというと必ずしもそうじゃないですが、ただその年の初物として今年はこんな出来ですよ、ということがお客様にお伝えできるのです。カカオも同じ植物なので本来なら毎年味が違うんです。でもその味の違いというのは味の安定性を重視するメーカーにとってはマイナスになりますから、いろんなカカオをミックスしたりして同じ味を作らなければいけない。そこを逆手に取ると一つの優位性になるんじゃないかと思います。
吉野氏: ええ。且つその熟成年も分かりますから。ウィスキーを仕込むブレンダーの方や、コーヒーの焙煎チャンピオンの方にお話を伺っても、結局どの方のお話も同じで、自分たちはブレンドしたり焙煎したり、いろんなことをして豆のポテンシャルを引き出し、より美味しくすることはできるけれど、でもその前提として素材が良くないと100点のものにはできないと仰るんですね。
30点の珈琲豆や30点の原酒をもらったところで40~50点のものしかできない。やっぱり素材自体の質が低ければそれ以上にはならないんです。そういう面でいうと、原材料にこだわっているというダリケーの強みを本来もっともっと活かすべきところではありますね。

吉野氏: 100億円というのは単純に考えて今の50倍、すると携わる農家の数は何千人、何万人になってきます。そうなると“市”まるごとや、県の半分といった数の農家の面倒を見ることができますから、100億を目指しそれが実現できたときに初めて、「インパクトを与えられたな」と実感するでしょうね。
吉野氏: ブランドというものは目に見えないがゆえに、分かっているようで分からないところがすごくあると思うんです。企業のブランドにしても、今見ている現在のブランドしか見えませんが、いろんな企業を見てこられた陶山先生をはじめとする皆さんは、さまざまな企業の成功事例や失敗事例、どういうところでここはブランド化したか、またはブランドを失墜させたかというところを時系列でずっと見てこられたからこそ分かるエッセンスというものをお持ちですし、またそのお話を伺うのもとても勉強になります。今後もこれまで以上に、「ダリケーだったらこうするべきじゃないか」と、より突っ込んだご助言をいただければと思っています。

本社:〒603-8205 京都府京都市北区紫竹西高縄町72-2
URL: www.dari-k.com
本店:〒603-8205 京都府京都市北区紫竹西高縄町72-2
祇園あきしの店:〒605-0821 京都市東山区清井町492-22
インドネシア現地法人:PT.Kakao Indonesia Cemerlang(KIC)
URL:http://www.pt-kic.com/
代表取締役 吉野慶一氏
1981年生まれ。栃木県出身。慶応義塾大学経済学部卒業後、 京都大学大学院にて地域研究(東南アジア)修士課程修了。その後、イギリスのオックスフォード大学大学院にて、社会政策を国際的に比較する比較社会政策修士課程修了。モルガン・ スタンレー証券株式会社 投資銀行アナリスト、 スピードウェル株式会社(投資顧問・ヘッジファンド)アナリスト、(財)統計情報研究開発センター研究員を経て、2011年3月にDari K株式会社を設立。
取材:2018年4月
| 2018/04/12 |