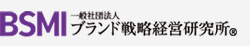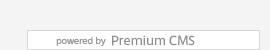HOME» ブランド対談 #03 »ブランドパーソナリティから見る次世代のマーケティング・リサーチ
ブランド対談 #03
ブランドパーソナリティから見る次世代のマーケティング・リサーチ

ブランドパーソナリティから見る次世代のマーケティング・リサーチ
取締役副社長の高栖祐介氏

高栖氏: ブランディングというと、商品をどうブランディングするかという部分に焦点を合わせることが多いのですが、今回『そのブランドを消費者はなぜ好きになるのか』という「なぜ」の視点からお話させていただきました。
お客様が実際に商品を手に取って買う瞬間というのは、あまり合理的に考えておらず、その商品が「良いか悪いか」というより「好きか嫌いか」で判断されています。それがその商品の持つ性格、つまり「ブランドパーソナリティ」なんですね。
ブランドパーソナリティは商品やブランドの便益や価値に対する納得と共感の前提になるものとも言えますね。つまりお客様に納得と共感されるためには、商品やブランドの持つパーソナリティが重要な要素になります。
従来のマーケティングリサーチは、マーケティングや消費者行動に関する何らかの理論や仮説を立て、それにもとづいて調査票を作成し、それから得られる定量的なデータを分析・解析するといった、定量調査が典型的なものですが、それについて少しお話を聞かせていただけますか。
高栖氏: 定量をどう捉えるかなのですが、人の話を聞くことの中でも「消費者の声を聞く」にはいくつかのパターンがあります。「聞く」は英語にすると「Ask」と「Hear」と「Listen」の違いがありますが、従来の調査の聞き方は「Ask」が多いんですね。つまり、問い教えてもらう。
アンケート調査にしても、「これについてどう思いますか」とお客様に意見を自由に書いていただいたり、選択肢を用意して選んでいただくというパターンが多いのですが、問うことによってお客様が頭で考え意識的に答えたことが、本当にその人を理解するのに正しい手法なのかということについては、私どもでは「正しく理解できない手法」と考えています。
人の行動は、無意識によって行われることが大半になりますので、意識的に答えることは、誇張してしまったり、思い違いをしていたり、こうなりたいといった願望が入っていたり、また良く見て欲しく見栄を張りたいといった意識も入ってしまいがちになります。
そうした意識の入った調査のデータを分析しても、元々の事実が入っているかどうかが判らない。それを鵜呑みにして商品化するしないの決断をするのは危険だと思います。
 陶山: 私たちもさまざまな定量調査を用いて研究していますが、そこには調査する側の理論や仮説があって、それを検証するために行うことが多いですね。
陶山: 私たちもさまざまな定量調査を用いて研究していますが、そこには調査する側の理論や仮説があって、それを検証するために行うことが多いですね。調査結果の定量データ化を統計学的に解析するというのもひとつにはあると思いますが、最初の調査票のところで、なんらかの調査主体の意識や目的があらかじめ入ってくると、果してそのデータは客観性を持つのかどうなのかということですね。
率直に消費者の声を聞く、その声を受け止めるということが重要で、何らかの意図が入ったりバイアスが掛かってしまうと、本来の購買行動を映し出せなくなってしまいます。
なぜある商品を選んだかということを、実際にお店で商品を手にしている場面ではなくて、WEB上などの調査票の質問項目を見ながら、「あのときはこう思ったのでは」と想像するんです。
その結果を集計して理屈付けしても歪曲されている場合が少なからずあり、事実が見えてこない。つまり正確に消費実態が把握できないということは仰るとおりですね。それでは消費者の「意見」や「意識的な言葉」ではなく、なぜこの商品を選ぶのか、どうして好きなのかの事実を理解するには、どのような調査やリサーチが必要になりますか?
高栖氏: 我々の考えで「行動はウソをつかない」というスタンスがありまして、人は口から発する言葉や文字や記号で答えることにはウソをつきやすい。つまりそれらの行為は意識が入っているので、自分が本来思っていないことを答えたり書けたりできるんですが、実際に行動したことにはウソはない、事実しかないと思うんですね。
今朝コーヒーを飲んだということや、昨日スーパーで何かを買ったとか、実際の行動にはウソはないので、そこの着目した調査を実施することが消費者の実態を見誤らないために必要だと思います。
高栖氏: 例えば野菜ぎらいのお子さんに野菜を食べさせたいというニーズがあって、それに対応する商品を作りたいといった場合、まず野菜ぎらいのお子さんを持つお母さんはどういう行動をとっているのかというのをフォーク化させるんですね。
一般的なパーソナルインタビューなどを行う際に、事実・行動ベースで聞いていくのですが、野菜を細かく刻んでハンバーグに入れたり、野菜ジュースにしたり、また野菜はこんなに体に良いんだよと子供に自分で調べさせたり、最近はライブ食といって、子供に自分で収穫させたり調理させたりといったことも出てきます。
そうしたフォーク化された行動の中から課題を見つけ出し、解決するソリューションとしての商品を提供する。ここでいうと、子供と一緒に安全に調理できて野菜ぎらいを克服したいという充足ニーズに応えられる商品を開発するということになります。
高栖氏: ええ、商品開発の一番はじめ、どういう商品を作るかというアイデア出しのところで今消費者がどういった実態なのかを把握するには、アンケート調査より行動観察といった事実を基点にした調査のほうが合っているのではないかと思いますね。
それには消費者の行動に寄り添って観察しながら、消費者自らが自助努力でやろうとしていることをキャッチし理解することが重要になります。
ともすればメーカーは、川上発想・シーズ発想になりがちで、消費者のことをあまりよく知らないまま技術や生産のロジックで行動しがちです。マーケティングは逆に消費者や市場が中心になります。
しかし、技術や生産、消費者や市場という両者のバランスをどうとるか、二つをどう両立させられるかをリサーチを通じて実現しようとなると、それはなかなか難しいのでしょうね。
 高栖氏:リサーチ会社の役割としては、誰よりも消費者のことを理解していなければいけませんが、メーカー側のことも理解していないといけないんですね。ある食品メーカーさんの場合では、製品に特化した成分があって、それに伴う特殊な技術を持っている。
高栖氏:リサーチ会社の役割としては、誰よりも消費者のことを理解していなければいけませんが、メーカー側のことも理解していないといけないんですね。ある食品メーカーさんの場合では、製品に特化した成分があって、それに伴う特殊な技術を持っている。
それを活かした製品を作るためには、消費者にどんなニーズがあって、どんな場面で受け入れられるかといった課題を見つけながら、横展開のご提案をするといったこともあります。
 高栖氏: そこはリサーチ会社として大きなミッションではありますが、中にはこの商品を市場に出すぞと意気込んでいるような事業部の方に言われた通り、それをバックアップするようなデータを切り取って出すといった場面も少なくない。そこはリサーチ会社側としては大きな課題かと思います。
高栖氏: そこはリサーチ会社として大きなミッションではありますが、中にはこの商品を市場に出すぞと意気込んでいるような事業部の方に言われた通り、それをバックアップするようなデータを切り取って出すといった場面も少なくない。そこはリサーチ会社側としては大きな課題かと思います。
昨年3月に発生した東日本大震災の後、仙台で2回、東京で1回グループインタビューを実施されましたね。生活者が震災後、ダメージを受けてから段階的に生活を再生させていく中で、どのように日常生活を元通りにしようとしてきたのか、あるいは従来とは違った生活を創出してきたのか、そこでどんな新しい価値観がライフスタイルが生まれているのか、を浮き彫りにする調査でしたね。
私自身はこういう調査はあまり経験したことがなかったのですが、個々の生活者の行動に密着してきちんと観察していく調査のスタイルがとても参考になりました。
高栖氏: あの調査は、被災された方の生活の価値観が、あのインパクトによってどう変化するか、変化しないのかをベンチマーク的に調査するものでした。震災3ヵ月後と半年後の2回調査しましたが、生活者の価値観というのは実はそんなに変化しない、つまり喉もと過ぎればじゃないですが、元の生活に戻そうとすると同時に、元の価値観に戻していこうとする傾向にあるということがわかりました。
 高栖氏:海外の場合、現地の食文化を知らずにデータを見ても深く読み取れませんから難しいんですね。翻訳された時点で既にその翻訳した人のバイアスが入ってしまうことが多いですから、原文をみて深く理解をしないと読み込めないと思います。
高栖氏:海外の場合、現地の食文化を知らずにデータを見ても深く読み取れませんから難しいんですね。翻訳された時点で既にその翻訳した人のバイアスが入ってしまうことが多いですから、原文をみて深く理解をしないと読み込めないと思います。
高栖氏: すでに多くのリサーチ会社が海外に出ていますが、私たちはどちらかというと定性調査が多いです。そこに言葉の壁もありますが、行動観察に言語はあまり関係ないんですね。
元来、行動観察の手法というのは文化人類学的なもので、アフリカの奥地に住む民族の生活を調べるといったものだったんですね。そのやり方を我々なりにマーケティングに転換して行っていることから、そうしたよくわからない文化を持つ人々の生活であったり、生活の価値観を導きだしていくには、行動観察は最適かと思います。
 高栖氏: 昔海外の企業が日本へ進出するとき、フランスのメーカーは日本人の行動がよくわからなかったんですね。彼らはモデルを作って定量調査をしたんですが、そのモデルに日本人の行動がなかなか合わず理解できなかった。
高栖氏: 昔海外の企業が日本へ進出するとき、フランスのメーカーは日本人の行動がよくわからなかったんですね。彼らはモデルを作って定量調査をしたんですが、そのモデルに日本人の行動がなかなか合わず理解できなかった。
それで進出をやめたということもありました。そこに何のモデルもなく、あえてありのまま関連性のないデータも含めて観察していった上で仮説を出していくという手法は、新しいところを理解していくには良いかと思います。
 高栖氏:現在のメーカー企業の組織では、経営トップは市場から掛け離れたところに位置づけされているんですね。ですがユニクロやAppleのように、消費者の変化をいち早く捉まえて、それに対応したビジネスモデルを構築することが重要だという時代になっています。
高栖氏:現在のメーカー企業の組織では、経営トップは市場から掛け離れたところに位置づけされているんですね。ですがユニクロやAppleのように、消費者の変化をいち早く捉まえて、それに対応したビジネスモデルを構築することが重要だという時代になっています。
その生活者の変化をいち早く正しく捉まえるためには、経営トップが事実をきちんと把握していなければいけない。今の組織構造だと、市場のデータに一番スイッチしているのが調査部なので、まず調査部が事実を吸い上げて、そのあと調査部の意見と一緒に事業部のほうに上がり、またその事業部の意見とともに経営トップ層に上がってくる。
そうするとどこかしらで事実が無くなってしまって、どんどん「ご意見」だけが上がってきてしまう。その事実と異なった「ご意見」でもって経営トップが判断してしまう。これが今の組織の現状です。
そこで調査部や事業部、営業販売部また協力会社であっても、誰もが同じ事実を浴びれるような組織を作っていかないと、時代の変化をキャッチできないですし見誤った判断をしてしまいます。これではどんどん時代の流れに置き去りになっていくんじゃないかと思いますね。
高栖氏:我々は事実と仮説が組み合わさったものを「意見」といってるんですけど、意見が加わることで仮説も加わることになり、意見はインフォメーションになるんです。
 データとインフォメーションは違いますから、インフォメーション(意見)だけだと元々のデータ(事実)が何だったのかがわからないままになってしまうんです。
データとインフォメーションは違いますから、インフォメーション(意見)だけだと元々のデータ(事実)が何だったのかがわからないままになってしまうんです。
その場合、情報を縮約整合しスクリーニングしてトップに上げる、つまり重要な情報とそうでない情報が歪曲されないで仕分けされていくプロセスが重要だと思ってしまいますが、そういうことではないのでしょうか?
高栖氏:経営者が必要なデータと、事業部が必要なデータ、営業が必要なデータというのは違うんですね。上がってくるそれぞれのデータというのは、自分の事業部にとって都合のいいデータだけが上がってくることが多い。
つまり自分の事業部に都合の悪いデータを排除してしまえば、なぜかその事業部がうまくいっていると見えてしまうとか、商品がこんなに盛り上がるように見えたりなどが起ってきます。本当に経営トップが判断するのに必要なデータというのは、事業部とはまた違う見方にありますからスクリーニングをかけないほうが良いと考えています。
高栖氏:そうですね。
高栖氏:時代の流れ的には今、店頭が注目されてきています。店頭でどういう購買行動が行われているのかという研究も弊社では行っています。現在、商品開発は消費者調査によって行われていますが、消費者ウォンツに対応するベネフィットとしての商品だけでなく、今後は店頭での購買行動調査によって商品開発するといった、バイヤーウォンツに合わせた商品開発も検討する必要があるのではと考えています。
「なぜこの店で買ってしまうのか」というパコ アンダーヒルの理論のように、購買履歴データに限らず、小売店頭でどのような購買が行われているかといったインストアに関する研究やリサーチは決定的に遅れていると思いますね。
肝心の流通企業も、本来は小売店頭についての情報は得やすい立場にありますが、たとえPOSデータやFSP(ID付きPOS)データを持っていてもそれを十分に活用できていない。どういう理論や調査スキーム、を用いていかに解析するかについては、あまり知らないということがあります。
当ブランド戦略経営研究所は産学連携の立場から企業などとコラボレーションしながら、FSPデータを商品・ブランド別、小売店舗別にパターンを分け、どんな顧客がいかなるライフスタイルにもとづいて商品・ブランドを選択しているのかをクラスター分析してプロモーションやコミュニケーションの方法を探るという調査研究もしています。
メーカーや流通業は、こうしたところをさらにきめ細かく知りたいでしょうね。そういう点では、御社はフロンティア・カンパニーと言って良いですね。
 高栖氏:エリアマーケティングというと、たとえば六甲なら六甲というエリアをどうしようかという話になるんですが、エリアも別の概念を持っているという考えもあります。
高栖氏:エリアマーケティングというと、たとえば六甲なら六甲というエリアをどうしようかという話になるんですが、エリアも別の概念を持っているという考えもあります。
たとえばセブンイレブンや、イトーヨーカドーを一つのエリアとして考え、その店舗周りの購買行動を分野として考えることも必要になるかと思っています。
高栖氏:メーカーさんのブランディングというと、これまでは広告宣伝費が大きなシェアを占めていましたが、今のように広告宣伝費が減少していく中でどうブランディングするか。そこで「店頭をメディア化する」動きが増えてきています。
店頭にいろんなサイネージやディスプレイが置かれ、お店に来られた方に何かを見せるといったことが増えていますが、従来のTVCMの宣伝広告と店頭で行われる宣伝広告、それらのメディアを通じたコミュニケーションをどうブランディングするかがこれから気になるところですね。
必ずしも計画購買でない商品であれば小売店頭は重要なダッチポイントの一つですから、まさに店頭が売りに繋がる場となり、また生活者とメーカーや流通企業との接する場でもありますから、そこをいかに活用しながらブランディングしていくかが、今後は非常に大きなテーマになりそうですね。

高栖氏: 意見をデータベース化するということは企業にとってなかなか難しいことでもありますが、一度データにしてしまえばそこにいろんなインデックスやタグ付けができますし、いろんな仮説の入った意見ではない事実があつまってきます。 そこで我々ができることは、経営トップがアクセスし易いしくみ、検索し易いデータベース化をご提案することですね。
また、たとえば食品メーカーさんだと、経営トップの方々は自分の奥さん以外に調理をしている姿をあまり目にすることがないでしょうから、他の主婦の方が自社の商品をどのようにして購入しているか、どう使っているのかを実際にお買い物に同行して体験していただくといったご提案なども行っています。

高栖氏: 両方必要ですね。ある食品メーカーさんの場合、経営トップの方とDOさん(ドゥ・ハウス運営「DOさん・ネット」主婦モニター会員)に、一緒にスーパーにお買物に行っていただいて、主婦がどんな風に買ったり選んだりしているのか、またその時の気持ちはどうなのか、ということを体験していただいたこともあります。
高栖氏: 我々もある程度の分類種別をしていまして、40歳代の主婦であれば、独身の方もいれば、既婚で子供がいる方いない方、パートに出ておられる方、継続収入のある方など、今現在置かれている状況によって価値観はある程度分けられると考えています。その価値観とその人(サンプル)のとった行動の中にギャップが生まれると、そこはチャンスだと考えています。
つまり行動が変化していても、最終的には普遍的に変わらない価値観のほうへ寄ってくる。そこに今この人はある状況によってこういう行動をしているけれど、本来のこの人の価値観であればこんな行動をするだろうという予測が立てられるようになる。そうした潜在的に眠っている価値観を理解していくということが、今後はかなり重要になっていくかと思います。
高栖氏: さまざまな分類で調査します。先ほどの40代主婦の場合だと、20%以上のボリュームでいくと4分類ほどに分かれますから、それぞれに持っている潜在的な価値観を予め調査してストックしています。
高栖氏: 定量データと、パーソナルインタビューによって得られたそれぞれの価値観の分類を持った上での調査になります。
高栖氏: 今生きている人の価値観はもう固まっていて、幸せになりたいとか、美しくなりたいとか、人が人として基本的に持っているニーズというのはあまり変わりませんが、これからの新しい時代を生きていく若い人たちや子供たち、次の世代の人たちがどういう価値観を形成していくのかを継続して調査することが、今後の課題だと思っています。
株式会社ドゥ・ハウス 取締役副社長
1973年 東京生まれ。慶応大学 総合政策学部卒。1997年 株式会社ドゥ・ハウス入社。事業内容:マーケティングサービス事業*生活フィールド、流通フィールドに対するクチコミプロモーションと定性情報リサーチ*デジタル&ネットワークをフル活用したマーケティングシステムの開発・実施*新時代のマーケティングを支える「多目的ネットワーキング
URL:http://www.dohouse.co.jp/
取材:2012年10月
| 2012/10/03 |