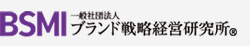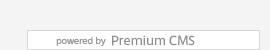HOME» ブランド対談 #11 »[ブランド対談]味の共通言語(味のものさし)で世界をつなぐ
ブランド対談 #11
[ブランド対談]味の共通言語(味のものさし)で世界をつなぐ
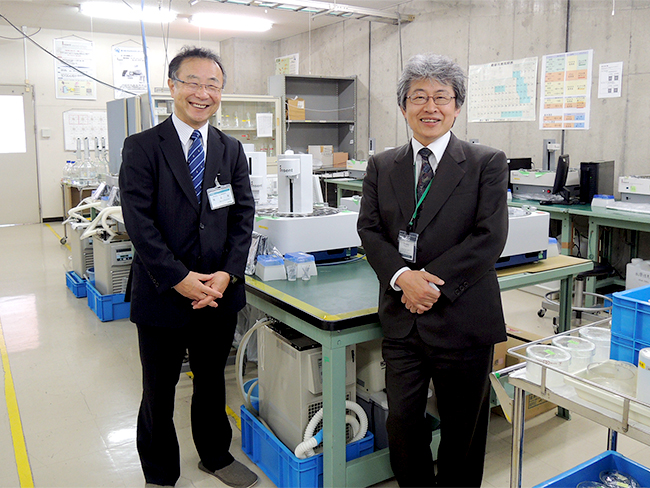
味の共通言語(味のものさし)で世界をつなぐ
今回のブランド対談は、一般社団法人ブランド戦略経営研究所理事長、関西大学 陶山計介教授が同社を訪問、株式会社インテリジェントセンサーテクノロジー(文中での呼称は”インセント”)の設立の経緯から理念とビジョン、味覚センサーの活用例、また現在の日本における食品産業などをめぐる動向や最新の現状をお伺いしました。
池崎氏:味覚というのは、従来主観的なものだと言われてきましたから、世の中に味の単位がありませんでした。そこで「味のものさし」を作りましょうということで、今から28年前、九州大学大学院の都甲先生と、アンリツ株式会社の中で共同研究が始まりました。その後、もっと責任持ってやっていきたいと思い、会社を辞め、味覚センサー事業を買い取って独立しました。
池崎氏:当時はいわゆる「選択と集中」と言われていた時代で、新しい事業というものは、3年から5年以内に事業化して儲からないとビジネスとは言わない、と考えられていた時代でした。当時は会社からも「こんな研究していていいのか」という意見もあったと思います。
ですが、すでにいろんな研究機関に機械を導入していましたし、私としてはお客さんも、“研究の同志”だったんですね。その方たちからも、将来、味の数値は絶対に重要になってくる、という想いがひしひしと伝わってきましたから、これは辞めるわけにはいかないと。そこでもう、私が全部自分責任とるからやらせてくれと会社に言った次第です。

池崎氏:いや実は、こういう面白いシーズがあるというだけで、私も、お客さまの研究所の方も、ここまでニーズがあるとは思っていませんでした。「なんかやっぱりこれからは絶対に必要だよね」という想いだけで、当時はまだそこまでしか見えていなかったんですね。
というのも、当時はまだ人口も増えていましたし、食品業界は商品を作れば売れていたんです。それがリーマンショックの後、人口がみるみる減ってくる。それでハッと気づいたら、少子高齢化社会になっているじゃないですか。これはもう本当の闘いになってきた、どうする?という・・・。
政府も、農水省がTPPを承認した後、そこから一斉に、農業も海外に打って出なさいということで地方創生をうたいはじめましたね。食品メーカーもうすうすそうなることは分かっていたけれど、ようやく「これまずいよね」と思い始めたんです。セブン&アイ・ホールディングスも2015年1月から、「地域性重視」といって全国を9ブロックに分けて組織を再編されましたからね。最終的に各県に分けるということですが、それもやはり少子高齢化になって、これからはおじいちゃんやおばあちゃんがお客様になる、ということを見据えているわけです。
実はその頃、2011年から2013年くらいですね、うちの会社は債務超過でつぶれかけたんです(笑)。社員は当時35人ほどいましたが、どんどん辞めていって、特に営業マンが先に辞めていきましたね。要するに僕は捨てられたわけです(笑)。その時に理念とビジョンを変えました。

池崎氏:そうです。それまでは、味覚センサーで味の共通言語を作っていきましょうというのが最初の理念でしたが、やっぱり味覚センサーはただのツールであって、どういう風に世界に貢献していきたいのか、どういう世界になって欲しいのかということを忘れていたんです。
その中でも、食に関する理念として「おいしいものを食べて笑顔」とありますが、その“おいしいもの”というのは、別に高級なものでなくとも、昔おかあさんが作ってくれたお弁当や、地域で食べていた懐かしいものなどいろんなものがある。それを実現するための共通の言語・単位を作るツールとして役に立ちたい、ということに変わったんですね。味覚センサーを作ることはシーズであって、ニーズじゃないんだと。
またその前の2020年には東京オリンピック・パラリンピックもありますし、2025年には大阪の万国博覧会が開催されるかもしれない。そこでのインバウンド事業として、食品メーカーは日本に来る外国人に、どう日本の食を経験していただくかという課題もあります。そこはどのように考えておられますか?
池崎氏:まず国内においては二つあります。一つは好みやテーストの多様化ですね。全国津々浦々同じ味というよりも地方の味。要は子どもの頃から食べていた家庭の味が求められています。ただそこには問題があって、いろんな地方の味となったとき、作るほうは理解不能で分からないんです。
もう一つは健康。今“ロカボ”(おいしく楽しく適正糖質)が流行っていますが、あれは一時のブームじゃなくて、切実な問題なんです。やはり政府も少子高齢化対策の一環で、女性が活躍する社会、定年年齢の延長と言っていますが、要は死ぬ間際まで元気。それが一番なんです。やっぱり“寝たきり老人”になるのは避けたい。
 政府としてはお金の問題もありますが、生活の質という面では、本人にとっても絶対に良いにきまっているんです。おいしいものを食べて、おいしいお酒を飲んで、みんなと会話して、仕事をして社会に役立って。身体に良いものを食べて健康になる、それが当たり前の社会になってくると思います。
政府としてはお金の問題もありますが、生活の質という面では、本人にとっても絶対に良いにきまっているんです。おいしいものを食べて、おいしいお酒を飲んで、みんなと会話して、仕事をして社会に役立って。身体に良いものを食べて健康になる、それが当たり前の社会になってくると思います。
ただ、やはりそこにも問題があります。これまで食品メーカーは、少しでも良い素材を使っておいしいものを作ってきましたが、今は全く逆なんですね。どんな食材でも美味しい味に、ただし健康に良いものにという。そこではこれまでの経験が使えないんです。そこで味覚センサーという道具が必要になってくる、ということです。
さらに、2020年の東京オリンピック・パラリンピックでは、日本は世界のショールームとなります。日本は安全だし、国民性も良い。日本は本当に素晴らしい、愛される国だというイメージですね。インバウンドで来る外国人に楽しんでもらうためには、食やレストランの在り方も変わってくると思います。
というのも、味付けの問題ですね。日本食は食べたいけれど、外国人には日本食は塩っぱいです。ベトナムやタイの人からすると2倍くらい違う。だから「日本食っておいしいと思ったけど、塩っぱい」。これは辛いですね。韓国の方もそうらしいですよ。
池崎氏:違います。日本人にとって“塩梅”、塩加減というものはものすごく重要じゃないですか。なので、おいしいと思って料理人や食品メーカーも作るけど、外国人からするとノーサンキュー。そこが元々ずれているんです。世界はもっと多様で、極端に違うこともある。それは国内の関西対関東といった話の比ではないんです。
2020年には、日本中をショールーム化して、都市だけでなく地方のおいしいものも食べていただきたい。農業も、これだけ安全に作って、しかも質が高い。日本食っておいしいし、健康に良いということを、世界中に知ってもらいたい。さらにそこからアウトバウンドするきっかけにしてもらいたいと思いますね。
 陶山:食の多様化ということで、国内でも東と西では味覚も違いますし、日本と海外ではもっと違います。さらに、おいしさと健康との両立も求められている。高齢化社会やインバウンド・アウトバウンドへの対応に向けて、問題をクリアするための客観的な基準が必要になってくる、そこが一番のポイントなんですね。
陶山:食の多様化ということで、国内でも東と西では味覚も違いますし、日本と海外ではもっと違います。さらに、おいしさと健康との両立も求められている。高齢化社会やインバウンド・アウトバウンドへの対応に向けて、問題をクリアするための客観的な基準が必要になってくる、そこが一番のポイントなんですね。また、今日本人の味覚がどんどん衰えてきているという話を聞きます。洋食化の中で醤油じゃなくてソースの味が好まれていますが、日本食には、こんぶ出汁やかつお出汁、一汁三菜といった伝統的な良さもある。
その研ぎ澄まされた味の感性や感覚を、機械できちんと客観化できれば、改めて日本食の良さを知っていただけますし、また国内でも日本食を見直すきっかけになってくるでしょうね。またそれが、食育や味育にも活かされるのではないでしょうか。
池崎氏:良いと思いますね。食の大切さを教育するなら、子どもの頃から薄味を食べて、本物を楽しんでもらうことが一番です。
池崎氏:中小企業ですと、開発から売り方、プロモーションまで関わります。ビジネスと直結するので、会社の戦略が変わってくるというのはすごく良いですね。一方で、これはうちの課題ですが、大手企業となると、ビジネス活用までというとまだまだ・・・。研究だけになりがちなので、もったいないですね。そこは今後強化したいところです。
 池崎氏:あまり具体的には言えませんが(笑)、やはり大手企業となると、まだまだ組織が“縦割り”になっているところが多いですね。マーケティングはマーケティング、商品開発部門から言われたから作って、営業がそれを売る。官能検査もしなければ、誰も食べてもない、ということもあるのには驚きます。というのも、今までは作れば売れていましたからね。何も困っていなかったのです。
池崎氏:あまり具体的には言えませんが(笑)、やはり大手企業となると、まだまだ組織が“縦割り”になっているところが多いですね。マーケティングはマーケティング、商品開発部門から言われたから作って、営業がそれを売る。官能検査もしなければ、誰も食べてもない、ということもあるのには驚きます。というのも、今までは作れば売れていましたからね。何も困っていなかったのです。
でも今後、本気で生き残りをかけるなら、昔に戻ってきちんとマーケティングして、対象を絞って、この商品はこのストーリーで、そしてみんなで食べて、ちゃんと調査しましょうよ、と思うんですね。味覚センサーで共通言語作るだけだと意味が無い。そこを今後さらにフォローアップしようと勉強会も開催しています。
池崎氏:対象によって内容は違います。マーケティング、開発、品質保証、そして営業と、それぞれ発想が全く違いますから。また、PB(プライベートブランド)とNB(ナショナルブランド)とでも異なってきますし、業務用向けもまた違うので、回数は増えますね。ただ、今当社が勉強会でお伝えしていること、データの取り方や使い方というのは、実はほとんどお客様から教わったことなんです。例えば、“食品設計”のプログラムもそうです。
池崎氏:食品設計というのは、実際に作ったものについて、いかに品質を下げず、コストを最適に効果的に作っていくかというプログラムです。例えば、あるコーヒー専門商社さんが、味覚センサーのデータを使って開発されたコーヒー設計のソフトがあるのですが、コーヒー豆はいくつも種類があって、ターゲットや費用対効果を図って、ブレンドを最適設計できます。でもブレンドだけならこれまでも、プロの方が自分の舌でおこなってきましたが、違うのはコストダウンできることなんですよ。
 池崎氏:そうなんです。つまりコストダウンの最適なやり方を探すという計算なんですね。それはブレンドのプロでもできません。原料も、豆を7種類くらい使うところを3つで再現できるという。それを教わったときはもう、これが本当に“使える”ということなんだと思いましたね。
池崎氏:そうなんです。つまりコストダウンの最適なやり方を探すという計算なんですね。それはブレンドのプロでもできません。原料も、豆を7種類くらい使うところを3つで再現できるという。それを教わったときはもう、これが本当に“使える”ということなんだと思いましたね。
コーヒー豆は相場で決まりますから、価格の上がり下がりがすごくあるんですね。ですから最初に設計した豆の値段が上がれば入れ替えなければいけない。でも入れ替えたら味が変わりますから、その度に設計をやり直さないといけない。そこで味も品質も変えない、しかもコストを下げる。そういうことは人間じゃなくて機械にさせれば良いんです。家電にしても車にしても、工学の世界はすべて機械で計算しているんですから。
池崎氏:そうです。でも数値化してしまえばできる。そこにデータマイニングやAI入れれば、今までできなかったことがもっとできると思います。データ化さえできれば、極端な話、プリンと醤油でイクラの味を作ることもできます。要は原料を変えても人間が同じように感じれば良いのですから。
池崎氏:そこはもう工業の世界です。少しハイクオリティなものをこの値段で楽しめるということですね。ただ、産地や原材料にこだわる商品となれば、その“こだわり”に価値があるので、そこはちゃんとお金と時間をかけて楽しんでいただければ良いんです。

池崎氏:これはもう切実な願いを込めたカタログです。全国のスーパーのバイヤーに向けて制作したものですが、実はこういうカタログは各県で出しているんです。ただしこれが他と違うのは、その中に味覚センサーのデータを掲載しているんですね。
例えば、この醤油は、某有名メーカーの醤油よりコクがある、ということが数字で載っている。それでバイヤーさんがちょっとなめてみて、「うちで置いてみようかな」というきっかけになる。こういうカタログは作り手の想いが強すぎるのですが、これだと数字や表で分かりやすく客観的です。
池崎氏:そこに掲載されている商品がTVやWEBに載れば良いんですが、そこまではなかなか大変です。これは今後の理想ですけど、こういう各県のいろんな商品がWEBで通販にのれば、それこそ全国のものを選べるようになりますよね。そうなると、名古屋のあれを食べてみたいとか、島根のこれを食べてみたいとか、それこそ多様性を楽しめる。そうなると地域の産品や銘品の提供のしかたも変わってくると思いますね。
池崎氏:今人類史上で初のことが二つ起きているじゃないですか。一つは、恐らく数十年後には全世界が豊かになってくる。もう一つは、その全世界が超高齢社会になる。この2つが同時並行しています。
そういう意味では、地域の多様性や、健康の問題を抱える今の日本はその先駆けになる。そこで日本の食品メーカーが大挙してこのチャンスを活かせれば、これは世界で通用するようになると思うんです。われわれとしては、世界が激動し、混沌としているときに、このツールを問題解決に活用していただきたい。それが最終的にわれわれのブランディングになると考えています。
池崎氏:将来の夢としては、やはり農業・水産業、そして食品工業のAI化ですね。単純作業や少し頭を使うことは道具を使えば良い。残るのは創造性だと思うんですね。「これとこれを組み合わせたら、もっとおいしいものになる」といったような、クリエイティブな発想にもっと時間を使って欲しい。そこで我々は道具で手助けしたい、というのが私の夢です。
池崎氏:クリエイティブというか・・・(笑)。ただ、お客さんのところに行くと、活用方法のヒントをいただけるじゃないですか。「あ、これはあれに使えるな」と。それでまた発想を発展することができる。それがすごく楽しいです。

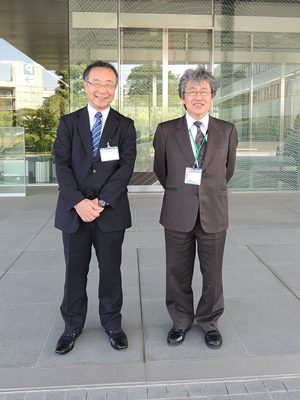 池崎氏:これはすごく重要なことですが、やっぱりマーケットインの発想ですね。もう“多様”を受け入れましょうということです。
池崎氏:これはすごく重要なことですが、やっぱりマーケットインの発想ですね。もう“多様”を受け入れましょうということです。
これからは本当の意味で世界と戦わないといけなくなりますし、また、世界を楽しんでいただきたい。日本はもともとプロダクトアウトの能力は高いんですから、これからインバウンドだけでなく、アウトバウンドが当たり前になってくると、マーケットインをしっかりやらないとダメ。そこは特に食品メーカーの皆さんをどんどん啓蒙していただきたいと期待しています。
それと、「ジャパンクオリティ」という言葉は絶対に使っていただきたいですね。世界で「ジャパンクオリティ」というのは既に通用していますが、なんと使っていないのは日本だけ。ベトナムやタイの工場には必ず「ジャパンクオリティ」と書いて掲げてありますから。せっかく世界一の「ジャパンクオリティ」なので、それをちゃんと使いましょう。
所在地:〒243-0032 神奈川県厚木市恩名5-1-1
http://www.insent.co.jp/
理念:「みんなが笑顔な世界へ」
おいしいものを食べて笑顔・飲みやすい薬で笑顔・安全な水や食べ物で笑顔
ビジョン:「味の共通言語(味のものさし)で世界をつなぐ」
主な受賞歴:2008年 財団法人りそな中小企業振興財団・日刊工業新聞社共催「第20回中小企業優秀新技術・新製品賞、技術・製品部門」優秀賞/2009年 経済産業省主催「2009年度第3回ものづくり日本大賞、製品・技術開発部門」特別賞/2009年 井上春成賞委員会主催「第34回井上春成賞」/2009年 中小企業庁主催、2009年元気なモノ作り中小企業300社「日本のイノベーションを支えるモノ作り中小企業」部門に選定/2009年 公益財団法人三菱UFJ技術育成財団から「平成20年度第2回研究開発助成事業」認定/2011年 飯島記念食品科学振興財団主催「平成22年度技術賞」
代表取締役社長 池崎秀和氏
早稲田大学理工学部電気工学専攻修士課程修了。1986年 アンリツ株式会社入社。味覚センサーの開発に従事。2002年 アンリツ株式会社退社、同年、株式会社インテリジェントセンサーテクノロジー設立。2005年 同社代表取締役社長就任。博士(工学)。九州大学客員教授。
取材:2017年4月
| 2017/06/28 |