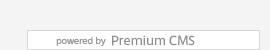HOME» 定例研究会開催レポート »【開催レポート】2018年10月度 大阪第5回フォーラム
定例研究会開催レポート
【開催レポート】2018年10月度 大阪第5回フォーラム

「一般社団法人 ブランド戦略経営研究所」では、大阪第5回フォーラムを2018年10月5日(金)に開催しました。今回のフォーラムは、関西大学平成28年度教育研究高度化促進費研究グループとの共催で実施いたしました。「地方創生とブランド・イノベーション」をテーマに、この分野の最先端で精力的に活躍しておられる三人の講師をお招きしました。
松下 正当研究所事務局次長(弁理士、古谷国際特許事務所)の司会のもと、まず当研究所の陶山理事長より大阪第5回フォーラム開催のご挨拶及び当研究所の事業概要、今回のフォーラムの解題がありました。
一般社団法人ブランド戦略経営研究所 理事長 陶山計介

今回の第5回大阪フォーラムは、私どもブランド戦略経営研究所は平成28年度から関西大学の教育研究高度化促進費を頂戴しておりまして、そのグループとの共催という形で開催をさせていただきます。
本日のフォーラムでは「地方創生とブランド・イノベーション」というテーマを掲げさせていただきました。21世紀は“地方の時代”と言われ、「地方の創生」や「地域の再生」は国政の上でも重要な柱の一つになっております。
2014年には「まち・ひと・しごと創生本部」が設立され、地方から日本を元気にしていく施策が進められました。今日の少子化ないし超超高齢化といった中で成長をどう確保するか、また各地域がそれぞれの特徴を活かし、自立的で持続的な社会をどう構築していくか、「地方と都市・世界をつなぐローカルブランディング」を実現することが急務となっています。そこで今回、それぞれの分野から地方創生あるいは地方活性化に多大な尽力をされております3名の講師をお招きしまして、これらのトピックスについて考えていこうと思います。
現在、第四次産業革命のもとAIやIOTが世界を大きく揺り動かせています。経産省の「新産業行動ビジョン」にもありますように、“スマートソサエティ”をどう実現していくかが喫緊の課題となっています。そうした動きの中において、地方というのはやや取り残され感があるように思います。3,000万人ともいわれるインバウンド需要も少しずつ地方にも普及伝搬してきていますが、グローバル化の荒波の中で地方がどのように自立的で持続的な発展を遂げていくか、ひいては我が国の成長力をどう確保し、少子高齢化をどう打開するかなど、さまざまな問題が山積しています。
そもそもブランドは、安心・信頼・バリュー・感動・憧れ・夢といった価値を提供する側と期待する側を繋ぐもの=ネクサスであり、またそれは企業にとって、あるいは地域や社会にとって、無形の資産としての価値、現在価値や将来価値をもたらすものとなります。さらにブランドは、企業にとっての目標であり競争手段の一つだけではなく、社会にとっても飛躍的なドライビングフォースの一つになっているともいえます。
それでは強いブランドを構築するためには何が必要なのでしょうか。マーケティング力や技術力、また流通力や店頭力、最近ではバズといったコミュニケーション要素も大事です。それだけではなく、「地域力」も重要な要素の一つです。企業とステークホルダーである地域の住民や商工業者、行政などがその地域の歴史や伝統文化とシナジー効果を発揮しながらブランドを共創する、地域が持つポテンシャルをどう活かしていくかということが強いブランド構築における大きな要素であると思います。
ブランドというと、ともすれば商品や企業を連想しがちですが、それは地域や都市または観光、行政といったところまで範囲が広がってきています。ただ、地域や都市のブランドということを考えますと、住民の方々にとってのブランドバリューと、観光客や来訪者の方々に対して提供するバリューとが、ともすればうまくバランスがとれていないこともあります。日常世界と非日常世界をどううまくバランスさせるかということもポイントのひとつになるかと思います。
それには、住民の方々が地元に愛着を持って地域や都市と自分自身とを一体化させていくこと。そして自信や誇りをもって自分たちの住んでいる町や村の良さを、ソーシャルメディア、最近ではFacebookやTwitter、InstagramといったSNSを使ってアピールすることが大切です。観光客や来訪者の方々に地元が持っている優れた価値を提供し、素晴らしい経験をしていただけるか、つまり、地域や都市の潜在的なポテンシャルをいかに顕在化させ、「知る・磨く・語る」のステップに沿ってその魅力を伝えるかが重要であり、またそれによってプラスのスパイラルが展開していくのではないか思います。
大久保 嘉洋氏 株式会社Oak-Jソリューションズ 代表取締役

『近大マグロ』を輩出した近畿大学水産研究所の歴史は、敗戦直後、近畿大学初代総長の世耕弘一氏の「海の畑を作る」という提唱のもと、魚の養殖を行う臨海研究所(後の水産研究所)が誕生しました。その後1950年代に同研究所が完成させた原田輝雄教授による「小割式網生簀養殖」は、世界で初めて、海の上に網いけすを浮かべ、その上で魚を飼うという画期的な養殖法でした。その養殖法で行ったマダイの養殖は非常に成功し、現在養殖されているマダイの遺伝子をたどると、ほぼこの近畿大学水産研究所で育ったマダイに辿りつくといわれるほどです。
そうした、「濡れ手に粟」のような大成功によって得られた成果は、次のマグロ養殖への研究資金となりましたが、順調だった養殖マダイに悲劇が襲います。1991年に全国の養殖場で「マダイマダイイリドウィルス」が発生し、売掛金の回収が困難になるだけでなく、補償問題にも発展して急激に研究所の収支が悪化してしまいました。さらに当時研究所のリーダーであった原田輝雄教授の急死や、景気低迷によるマダイの価格低下、外国産養殖魚の台頭、競合養殖業者の増加など、不運の時代を迎えます。
しかし研究所では、やはり過去の成功体験もあり、「良いものを作っていればいつか売れる」という思いが蔓延しており、赤字が続くばかりでした。とうとう当時研究所の事務長だった大久保氏は、「これ以上の赤字が続くと研究所の閉鎖もありうる」と大学本部から通達を受けてしまいます。一般養殖業の企業とは異なり、漁場を広げることができない大学の研究所で収支を上げていくには、研究所が養殖している魚の価値を上げるしかない。そこで当時研究中だった養殖マグロの単価を上げるべく、「ブランディング」ということが考えられました。とはいえ大学の機関。研究所なんだからお金儲けはしなくてもいいという考え方や、「ブランディング」なんて専門外なことはできないという意見も多かったそうです。

そうして2001年、同研究所は世界初のマグロ完全養殖に成功します。当時はテレビや新聞等で大々的に報道されました。大久保氏をはじめ、研究所の方々も「これで収支が改善できる」と大いに盛り上がったそうです。その養殖マグロが25~30kgの成魚になるまで2年3ヶ月。いよいよ売りに出そうと大阪の卸売市場へ意気揚々と向かった大久保氏は、卸業者から「ただの養殖マグロじゃないか」と言われてしまいます。技術的に高く評価されても、実際の商品としてのブランドは簡単にできるものじゃないと痛感されました。
そこで大久保氏はマグロの流通を知るべく、仲卸業者や小売業者の意見や、消費者であるお客様の声を聞くために全国を回られましたが、「これが近畿大学の水産研究所のマグロです」と話をしても、なかなか良い反応はありません。そんな中であるお客様の一言、「大学が作ったマグロ?なら安心よね」という言葉で、安心を見える化することを思いつきます。また知人が教えてくれた、「ある寿司屋が近大のマグロを握りながら、このマグロは大学出てるんやてって言っていた」という話にヒントを得て、大卒マグロ、安心安全のQRコードを掲載した卒業証書をつけて販売することを考え出されました。この卒業証書のついたマグロは、百貨店に出すとたちまちブームとなり、現在の『近大マグロ』ブランド化のスタートとなりました。
ここで大久保氏は「ブランディングには大きく2種類がある」と言います。一つは品質重視型。商品は川上から川下へと消費者の元へ流れますが、その段階の中に荷受業者・仲卸業者・小売り業者がいます。品質重視型の例として、大間のマグロはどの流通過程においても、「大間のマグロは美味い」という認識があり、自然とブランドが消費者まで伝わっています。一方、『近大マグロ』の場合、話題になることで、「『近大マグロ』って話題になっているけど、うちにも手に入らないか」と、小売業者から卸売業者へ、つまり川下から川上へと上がってくる。これを戦略重視型と言います。その後、現在のように『近大マグロ』ブランがド確立され、それに伴い近畿大学自体も、入学志願者数が5年連続日本一と飛躍的にアップしました。今は近畿大学を離れておられる大久保さんは、そのブランドストーリーを本にして出版され好評を得ておられます。
最後に、「常識や固定観念を破ることをまずやらないとブランディングなんてできません。また、ブランドというのは作るだけでは何の意味も無いんです。実践してさらに継続していかなければいけない。ブランディングは、ブランド作りが目的ではない。ブランドによって得られるベネフィットを意識しながらブランディングを進めていただきたいと思っています。」という言葉で締めくくられました。
株式会社Oak-J(オークジェイ)ソリューションズ 代表取締役。
Profile: 1954年生まれ。三重県出身。三重大学農学部卒。元近畿大学職員。近畿大学水産研究所在職中、「養殖魚でブランド化なんて無理だ」といわれるなか、「近大マグロ」のブランド戦略を企画・立案からプロデュースし、全国的に知られるメジャーブランドへと成功に導くとともに、商品だけでなく大学全体のコーポレートブランド戦略の礎となる。大学退職と同時に起業し、独自に考案したオークジェイ戦略モデルを使ったブランドづくりのコンサルティングを中心に講演、研修活動を展開。現在に至る。著書は『卒業証書をもらったマグロ』、『欲しいと言わせるブランドづくり』『売れるブランドの仕掛けづくり』
山本典正氏 平和酒造株式会社 専務取締役

日本独自の伝統産業でありながら、衰退が危ぶまれる日本酒業界。その生産量は1972年をピークに7割激減し、現在も下がり続けているといった状況です。その中で、酒蔵の4代目として家業を継がれた山本氏は、日本酒の未来にも明るい光を感じられています。
和歌山県海南市にある平和酒造は、元は室町時代から続くお寺の家系。1928年、山本さんの曽祖父が酒造りを始め、創業90年になる酒蔵です。和歌山県は日本酒の2大名産地、灘・伏見に近い地域であることから、長く伏見の酒蔵の下請け蔵として営業を続けていました。3代目となる山本氏のお父様が蔵を継がれたのは1979年。低迷する酒蔵を盛り返そうとパックの日本酒、さらにはパックの梅酒を自社商品として開発されますが、規制緩和による価格低迷や、大手メーカーによる大量生産、大量消費型のものづくりに押され、「和歌山の酒」の製造販売は苦労が絶えなかったそうです。
京都大学卒業後、東京のベンチャー企業に勤めていた山本氏が実家の酒蔵に戻ったのは2004年。当時はパック酒の製造が99%でしたが、1994年から梅酒造りも行っており、夏は梅酒、冬は酒造りと、当時から通年雇用も実施され、正社員の蔵人も何人かおられたそうです。ただ、4代目として酒蔵に戻ったものの状況はますます厳しくなる一方。そこで山本氏は策を練ろうと考えます。
―――「父のやり方を私は否定するつもりはありません。父の時代はそれでよかったと思います。ただそういう時代は終わりつつある。灘・伏見の酒蔵を目指すのではなく、和歌山の強みを活かした酒蔵を目指さなければいけない。和歌山は梅の産地ですから、これを強みにして本当にこだわったものを作ればお客様に届くんじゃないかと。そうして作ったのが高級リキュール『鶴梅』です。」―――
折しも当時は梅酒ブームの到来もあり、『鶴梅』は発売以来、楽天市場のリキュール部門に14年間1位に輝き続けています。その成功の裏には、地域で1店舗のみ販売するという「特約店制度」を敷かれたことも大きな要因の一つでした。
―――「心掛けたのは、すぐ売れることではなく、できるだけ長く売れるようにということで特約店制にしました。すると特約店の酒屋さんにとって売りの武器になるんです。『このお酒すごいんやで。和歌山の酒蔵が作った梅酒なんや。よかったら飲んでみて』と頑張って売ろうとしてくれる。そうしてブランドイメージを上げていきました。するとおもしろいことが起きてくるんですね。父の時代にはけして言われなかった、『ありがとう』という言葉をお客様からいただけるようになったんです。」―――
そうしてある時山本氏は、お客様である酒屋さんから、「よかったら日本酒も売るから持ってきてよ」と言われます。ですが、すぐに持っていけなかったと山本氏は言います。もし自社の日本酒が美味しくなければ、これまでの「ありがとう」と言ってもらえる関係が崩れてしまうかもしれない。そこで全国の酒蔵を周りながら酒造りを学び直し、3年かけて生み出されたのが「紀土(キッド)」という日本酒でした。

ここ近年、日本酒ブームと言われていますが、販売数は45年間下がり続けているものの、特定名称酒の分野は伸びていると言います。衰退産業だと言われているからこそ、さまざまな戦略が生まれ、新たな技術もどんどん開発されてきています。こうした製造のイノベーションによって特定名称酒の伸びは今後の続くだろうと山本氏は予測しています。しかし現在日本酒業界の7割を占めているのが、大手メーカーによるパック酒。残り3割の分野が業界をけん引するのはまだまだ先ですが、その伸び率のスピードをいかに上げるかが重要だと言います。
将来の日本酒業界にとって光となるのは、技術開発だけでなく、ものづくりに憧れる若者の増加にもあります。山本氏の平和酒造にも、全国から入社希望のエントリーが入り、多いときは2000名の応募があるそうです。その中で採用するのは1~2名。大学新卒のみを採用、蔵人は全て正社員雇用になります。蔵人たちのモチベーションと責任感を上げる一環として平和酒造では、「責任仕込み」という蔵人一人一本酒造りの全てを任せるということもされています。また、製造マニュアルを開発することで、蔵の中で技術の切磋琢磨が生まれるようになったそうです。
最後に、「価値のイノベーション」を起こすために、山本氏は、全国の若手の蔵人たちと連携しながら、「若手の夜明け」や「Aoyama Sake Flea」など、さまざまなイベントを開催したり、また世界中に日本酒を紹介しながらセミナーも行っています。山本氏が目指す市場は、従来の日本酒を飲む方々ではなく、若い世代や女性、また海外といった新たなパイを作りながら狙っていくと言います。特に海外においては、いつもの日本酒の瓶が海外に出た途端「カッコいい」と認識されています。同じものでも見る目によって変わる。その価値のイノベーションこそ、これからの日本酒業界の未来を担うといいます。
―――「ワインの発信拠点といえばフランスというように、日本酒の発信拠点はもちろん日本。それは日本がプラットホームとして持てる、数少ないものの一つになるんじゃないかと思うんです。現在、フランスのワインの輸出額は年間約8000億円。レートによっては1兆円近くなるんですね。対して日本酒の輸出金額といえば185億円。
世界で今起きている和食ブーム。もっともっと日本酒ラバーが増えていき、仮にこの金額がワインほどにまでなるとどうなるか。日本に約1兆円の輸出産業が生まれる可能性もあるんです。さらにこの輸出産業は自動車と違い、すべて日本で原材料から製品までが生産されている。田んぼがあって稲作が行われて、地方の農村が輸出産品を作っていけるということになるわけです。
15年前、実家の酒蔵に戻った頃は正直、「都落ち」した気分もありました。地方、伝統産業、ものづくり、というとネガティブなイメージを持っていたと思います。でもその実家の酒蔵に戻ってみたらこんなチャンスがあった。今はネガティブワードを感じることは全くありません。地方にはもっともっとブランド化できるものがまだまだ眠っている。こういうことは日本にはすごくたくさんあるんじゃないかと思います。」―――
平和酒造株式会社 専務取締役
Profile: 1978年生まれ、和歌山県出身。東京のベンチャー企業を経て、2004年に平和酒造へ入社。それまでの廉価な大量消費のためのお酒ではなく、日々の人生に豊かな彩りを添えられるお酒を届けたいとの想いから「紀土」「鶴梅」を立ち上げ。近年ではクラフトビール「平和クラフト」の発売も開始。“斜陽産業“と言われる酒造業界において新風を吹かせるべく、若い蔵人の育成にも力を注ぐ。伝統と革新をもって酒造りを行う一方、日本酒の魅力を伝える活動を行っている。著作に『ものづくりの理想郷』『メイドインジャパンを僕らが世界へ』
岡田 学氏 西日本旅客鉄道株式会社 営業本部 瑞風推進事業部 部長

2017年6月17日に運行を開始したJR西日本の「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」は、京都駅・大阪駅と下関駅を発着駅として、山陰山陽エリア間を走行する豪華クルーズトレインです。2017年5月に運行を開始したJR東日本「TRAIN SUITE 四季島」と、2013年に運行を開始したJR九州「ななつ星in九州」との3大豪華クルーズトレインは、日本のクルーズトレイン時代の幕開けだと言われています。今回岡田氏からは、なぜJR西日本がこうした豪華な列車を運行されたのか、またどういったことにこだわっているのか、そのブランド価値とは何かを、最初に「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」プロモーションビデオを拝見しながらご説明いただきました。
JRグループの中において、首都圏を抱えるJR東海やJR東日本では、新幹線というビジネスや私用の利用客が確たる収益の柱を担っていることに対し、JR西日本は、日本における世界文化遺産の半数を抱えるという観光素材が豊富なエリア力を活かし、観光利用客のパイを増やすということに注力されたということ、それによって山陰山陽エリアの地域活性化に貢献したいという狙いが背景にありました。また、豪華客船「日本丸」や「飛鳥」といったクルーズ船の人気に見られる日本におけるクルーズ文化の浸透も、「瑞風」の誕生には外せない背景でした。
「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」は、かつての人気を博した初代「トワイライトエキスプレス」の後継車両として、2011年からそのプロジェクトがスタートします。初代の「トワイライトエキスプレス」は、美しい景色の車窓・本格的フルコースの食事・そして格調の高い上質な内装の車両という3つの価値で高評を得ていましたが、「瑞風」はその伝統を継承しつつ、そこにプラス、沿線エリアの魅力発信という新たな価値を担います。
この「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」のコンセプトは、「ホテルのような上質さと心休まる懐かしさを感じる列車」です。まずはその豪華な車両とサービスをご説明いただきました。デザインの総括は、京都迎賓館などを手掛けた建築界のカリスマ浦一也氏。「走るホテル」ではなくあくまでも「ホテル」の意匠にこだわった内装は、“美しい日本をホテルが走る”というコンセプトをまさしく具現化されています。また、新幹線N700系を設計されたインダストリアルデザイナーの福田哲夫氏も参画され、展望デッキや車両の両側が開く可動壁の窓など、旅の楽しさをアップする設計になっています。
また、この「瑞風」は10両編成で全てが個室。最大でも34名の乗客定員となりますが、サービスクルーは16名。実にお客様2名に1人のクルーがつくという贅沢な仕様です。食事も関西の著名美食家、門上武司氏プロデュースのもと、和食は京都の料亭「菊乃井」の村田吉弘氏、洋食はレストラン「HAJIME」の米田肇氏と、ミシュラン3つ星のお二方が監修されています。
現在「瑞風」は片道コースと周遊コース合わせて5コース。1日1回は停車駅より専用の「瑞風バス」に乗車して地元を観光します。観光地においては一般客には公開していない場所や、地元の人たちとの交流もあり、従来の旅行にはない特別感のある趣向を凝らしたものになっています。また発着駅も、「瑞風ゲート」を特別に設け、ホテルグランビア内でチェックインし、そのままホテルの室内が動き出すような臨場感にもこだわっています。

さらに、この「瑞風」が担う重要な価値の一つは、沿線の観光・食材・産業にスポットを当てていることです。世界文化遺産だけでなくその周辺の美しい観光地、また文化的価値があるにもかかわらず、これまでアクセスの難しさから無名に近かった観光地を訪れたり、非常にこだわったものづくりで生産されているものを車内の調度品として使用する、また地元の食材を使った食事など、「瑞風」を媒体とすることで、それらにスポットが浴びることを目指されています。
観光については、世界文化遺産だけでなく、地元の自治体や住民の方々など地域との連携によって沿線の新たな観光スポットを発掘、整備されてきました。その例の一つに、かつて旧国鉄時代の無人駅だった東浜駅は、県や国とも連携し、美しい駅舎、海岸の砂浜へと続く遊歩道、そして朽ちかけていた公共建築物をイタリアンレストランに変え、「瑞風」が停車する素晴らしい観光地に変身させています。
―――「観光というものは人的・経済的・文化的なものを含めて、地域活性化に大きく関わってくるものです。地域と連携して人の交流を拡大し、地域を活性化する。それがひいては地元と当社の共通の目的となりWin-Winの関係が築かれます。それによって持続的な発展を図っていく、「瑞風」はその取り組みの一つです。」―――
また、この「瑞風」のブランディングについて、岡田氏は4つの狙いを挙げられました。まず1つ目は、お客様に対しこの「瑞風」を通じて改めて鉄道の旅の良さを体感していただきたいこと。2つ目はこうした豪華な列車を運行しているという企業としてのブランドイメージの向上。3つ目は「瑞風」が運行することによって沿線地域に観光客が増え、また調度品や食材に沿線のものを使用することによって地域活性化に寄与したいということ。最後に社員に対する狙い。こうした豪華列車を走らせている会社に入りたいと、優秀な人材が確保できるということや、また現在の社員に対しても誇りに感じて欲しい、そんな狙いも込められています。
―――「やはりその豪華さだけではなく、「瑞風」にかかわる人たちの想いをさらに強くすることが、JR西日本への信用、ひいてはブランドを高めることになると考えています。」―――
西日本旅客鉄道株式会社 営業本部 瑞風推進事業部 部長
Profile: 1991年東北大学経済学部卒業、JR西日本入社。営業部商品企画・宣伝、大阪支社関西空港駅長、和歌山支社人事課長、西日本ジェイアールバス㈱取締役企画部長、和歌山支社副支社長などを経て、2015年6月より現職。

続いて、本日の3名の講師、大久保氏、山本氏、岡田氏と、陶山理事長とのパネルディスカッションを行いました。まず、地方創生にまつわるさまざまな困難や厳しい問題に対してどう取り組んでこられたかについてお伺いしました。
大久保氏からは、近畿大学水産研究所の成り立ち、初代総長の提案によって大学と和歌山県白浜町の漁協の人たちとの連携がスタートした経緯や歴史についてお話いただきました。
山本氏からは、地方の衰退には「市場の喪失」と「働き手の不在」という2つの要因があると述べられました。それに対して山本氏は、今は「良い大学を出て良い会社に入り定年まで勤める」という昭和のモデルが崩れ、自分の人生をどう生きていくかを考える若者が増えている。ものづくりを選ぶ人もまた増えてきていると言います。そうした中でいかに全国から人を集めるか。それには自分たちのものづくりの理念をメッセージとしていかに伝えていくかが重要だと言われます。また市場の喪失については、ライバルとなるのは同業他社ではなく、お酒について否定的な考え方そのものであるというお話をされました。
岡田氏からは、「瑞風」が今回チャレンジスポットとしてご案内する奥出雲の「室山農園」について事例を出されました。かやぶきの家で、地元の素材を使い地元の方たちが作る食事を、豪華列車のお客様に提供することについて、当初は不安視する声もありましたが、実際は非常に好評を得て、さらに地元の方々がお客様とのコミュニケーションを楽しんでいるというお話をいただきました。


また、地方のマーケティングを世界ブランドとして展開させていくにはどうしていけばいいか、その際に何が必要になるのかについてもお伺いしました。
山本氏からは、作り手にとってブランドとはものづくり。自分たちの強みは何か、どうすればお客様にとって魅力的なものになるのかを考えていくことの延長がブランド作りだということ。また、岡田氏からは、評価されるのはハードではなくてソフト。心からお客様におもてなしをすることでリピートにつながっていく。そういう営みがブランドにつながっていくのではないかというお話をいただきました。最後に、大久保氏からは、ブランディングに必要な6つのポイント、「SPNSOR」(S=シンプル、P=プロモーション、N=ニーズ、S=ストーリー、O=オンリーワン、R=リザルトチェック)についてお話いただきました。

Q:山本さんに質問させていただきます。大学新卒の中から採用をということですが、2000名の応募から1~2名ということで、山本さんはどこを見てどのような判断をされて採用されているのですか
山本:人材系のベンチャー企業で働いていてつくづく分かったのは、人って本当に一緒に働いてみないとわからないというのが正直なところです。でもまずは自分たちが目指していきたいビジョンに共感していただける人。それが一番大事だと考えています。また、新しいことにチャレンジしたいという自発性みたいなところも重要視しています。
Q:「瑞風」を運行するにあたりいろんな地域の方々と協力体制を築いてこられましたが、どんなことを心がけておられましたか?
岡田:私どもがいつも心がけているのは、「瑞風」と組んで良かったと思っていただくことです。「瑞風」は30名ほどのお客様しかお乗せしておりませんので、その方々だけで地元が潤うことはありません。最終的に地元が潤うためには、やはりマスのお客様に来ていただかなければならないのです。そこで、「瑞風」が訪れる観光地に行くことで、少し「瑞風」気分を味わえるような旅を旅行会社に商品化していただいたり、「瑞風」を使った旅行番組や雑誌等で地元をご紹介することで、地元にお客様が来てくださる。そうしたメリットを感じていただければいいなと考えています。
最後に閉会の挨拶として、松下 正当研究所事務局次長から各講師、参加者の皆様への謝意や各講師への感想が述べられ、閉会となりました。

今回の大阪第5回フォーラムでは、「地方創生とブランド・イノベーション」というテーマで、お三方にお話をいただきましたが、それぞれの分野で素晴らしい活動をされ、事業の中にしっかりブランドを位置づけておられるとあらためて感じました。ブランドにおいてシンボルやロゴマークも重要なアイテムの一つではありますが、そのベースになるものとして、スピリッツ或いはアイデンティティというものも不可欠です。なかでも人を通した交流や共感が最終的な決め手になる要素ではないかと思います。自分たちのブランドの持つ良さや違いを「知る・磨く・語る」でさらに進めていく。こうしたいろんな取り組みこそがまさにブランディングであると考えます。ご講演いただいた三人の講師には厚くお礼申し上げます。